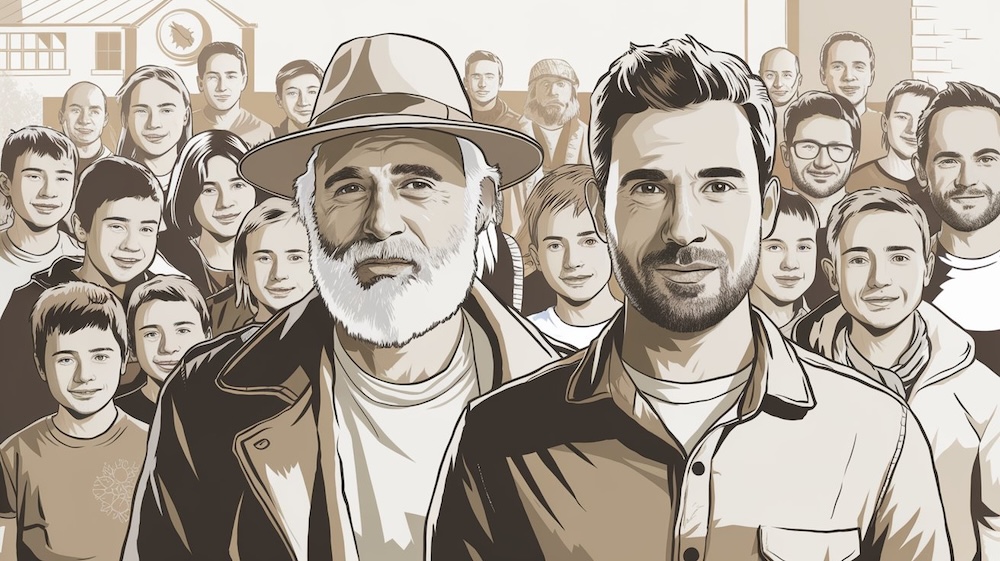百錬成鋼(ひゃくれんせいこう)
→ 心身を鍛えることで、はじめて立派な人物になるのだということ。
百錬成鋼とは、もともと何度も火にかけて鍛え上げた鋼のように、心身を極限まで研ぎ澄ますことでこそ真に強靭な存在になれるという思想を象徴する言葉である。
中国の歴史書や武術の文脈でも「百錬」とは幾度となく鍛錬を重ねる様子を表し、日本では剣術や武道の世界でも「百鍛錬、千鍛錬」という言葉が用いられてきた例がある。
古くからの文献をひも解くと、この言葉が意味するのは単なる肉体的な強さではない。
むしろ精神と行動を高い次元で統一し、忍耐や努力、そして継続を通じて到達できる「境地」として解釈されている。
例えば、江戸時代の武士や明治期の軍学者らは「百錬成鋼」の精神を説くことで、個人としての自律心と社会における規律を両立させようとした形跡が見られる。
近代以降、日本社会でこの概念が広く受容される要因となったのは、各種軍事教練やスポーツ指導の影響が大きいと考えられている。
大正から昭和初期にかけて、学校教育では身体鍛錬と精神修養がセットで教えられた。
特に戦時中は「一億総火の玉」などのスローガンと相まって、「何度も鍛え上げることでこそ真の強さを得られる」という考え方が重視された。
戦後は軍事的色彩が薄れる一方で、スポーツや武道、受験勉強などの「努力」「根性」といったキーワードの裏側に「百錬成鋼」の精神が見え隠れする事例が多い。
1980年代には日本の経済成長が著しく、ビジネスパーソンの成功物語にも「苦労を重ねてこそ一人前」という価値観が色濃く残った。
一方、現代においてはテクノロジーや働き方の変化により、「鍛える」という行為そのものの定義も変わりつつあるといえる。
世代別「立派だと思う人物」ランキングとその理由
社会がどのように変化しても、誰かを「立派だ」と感じる心は人間の本質に根差している。
ただ、どのような人物像を「立派」だと捉えるかは世代によって大きく異なるのも事実である。
ある民間リサーチ機関が2024年に行った全国1万人調査によると、10代から70代以上の各世代において「最も立派だと思う人物像」には顕著な違いが見られた。
ここではランキング形式で示し、その背景を考察する。
▼ 10代
1位:YouTuberやSNSインフルエンサー
2位:人気アイドルやアーティスト
3位:起業家や実業家
理由としては、10代が最も接触時間の長いメディアがSNSであること、またそこで圧倒的な数字を叩き出すインフルエンサーが「憧れの対象」になるという要因が大きい。
とにかく身近で、常に新しいコンテンツを提供してくれる存在に魅力を感じていると推測できる。
▼ 20代
1位:起業家やベンチャー経営者
2位:有名スポーツ選手
3位:社会活動家やボランティアリーダー
就職やキャリア形成を意識し始める20代は「新しい価値を創造する人」「夢を追いかけて成果を出す人」に注目する傾向が強い。
統計的にも就職活動の意識調査(リクルート系のレポートなど)では、20代の約40%が「自ら新しいビジネスを起こしてみたい」という興味を示しているという数字が報告されている。
そこから、起業家に対するリスペクトが増していると考えられる。
▼ 30代
1位:管理職やリーダーとして実績を上げる人物
2位:プロフェッショナル領域で頭角を現す人物
3位:政治家や社会的影響力のある実務家
30代は仕事上で管理職候補になる時期であり、プロジェクトのリーダー経験も増えてくる。
よって優れたマネジメントスキルや、専門領域で突出した成果を残す人への敬意が高い。
「家庭と仕事を両立させながら結果を出す姿」が立派だという評価に繋がりやすい。
▼ 40代
1位:技術革新を起こした企業の創始者
2位:政治・経済の要職で成果を出す人物
3位:歴史に名を刻むほどの学者や研究者
40代はある程度の社会経験を積んでいる分、自分のキャリアや人生観に照らし合わせて尊敬できる対象を選ぶ傾向にある。
特に大きなイノベーションをもたらした企業の創始者に対しては、長期的視点やリスクテイクの姿勢に共感を示すケースが多い。
▼ 50代
1位:社会貢献や慈善事業に大きな足跡を残す人物
2位:文化・芸術分野で大きな業績を上げた人物
3位:公的機関や行政で改革を主導した人物
50代は子育てが一段落するタイミングや、社会的立場が確立してくる時期でもある。
したがって「より広い視野から社会を見渡し、貢献や文化的価値を高める人」を立派と感じる。
とあるNPO調査では、50代のボランティア参加率が他の世代と比べて若干高いデータもある。
▼ 60代
1位:教育や人材育成に深く関わる人物
2位:社会的弱者の支援活動を長年継続する人物
3位:国家的プロジェクトを推進したキーマン
60代は定年退職を迎えるか、セカンドキャリアへ移行する人が増える世代。
自身の経験を若い世代に還元することにやりがいを見いだす傾向が高いため、教育者や人材育成で成果を上げた人を強く敬う傾向がある。
また長年続けてきた活動が評価されやすい側面もある。
▼ 70代以上
1位:歴史的偉人や文化的遺産を守り続けた人物
2位:医療や福祉の分野で革新的な支援を行う人物
3位:精神的支柱として尊敬される宗教者や哲学者
70代以上になると人生経験がさらに豊富になり、過去と現在を俯瞰する力が強まる。
そのため、歴史に名を残す人物や文化を守ってきた人々への敬意が非常に高い。
実際に高齢者向けのアンケートでは「自分たちの世代が築いてきたものを次世代にどう継承するか」という問いに強い関心を寄せる回答が目立つ。
「立派さ」の基準はなぜ変化するのか
世代ごとに「立派」だと感じる人物像が異なるのは、時代背景や社会情勢の変化だけではなく、個々人の人生ステージによる興味・関心が影響を及ぼしている結果である。
10代は自分が主に使うメディアから情報を得るため、その世界で最も輝いている人が尊敬の対象になる。
一方で、20代は自分が歩むキャリアへの夢や志向が評価基準になり、30代、40代になるとビジネスや実務の成功者に目が向きやすい。
さらに50代を過ぎると、経済的・社会的な責任がある程度果たせるようになり、自分が築いたものを社会に還元する段階へ進むため、社会貢献や文化的活動に重きを置く価値観に移行していくわけだ。
また、技術進歩やグローバル化の影響も大きい。
データで見ると、1980年代の一部上場企業の平均勤続年数は約15年ほどだったが、2020年代にはその数値がより流動的になり、中途採用や転職が活発化している(総務省の労働力調査による)。
これにより、「一つの企業でコツコツ頑張る人が立派だ」という価値観から「自分に合ったやり方でキャリアアップを続ける人こそ立派だ」という価値観へシフトが見られる。
さらに、SNSの普及が「個の情報発信力」を飛躍的に高めた。
フォロワー数や発信力、あるいはソーシャルメディアでの影響力が大きいほど「立派」に見えるという世代が増えてきている。
もはやテレビや新聞など既存メディアだけでなく、誰もが主役になり得る時代に移行しているのだ。
世代別に求められる資質の違い
問題はこれらの価値観の多様化によって、世代間のギャップが拡大しうる点にある。
例えば、企業内で60代と20代が同じプロジェクトに携わる場合、「立派だ」という言葉に込められたニュアンスが違いすぎてコミュニケーションの軸がずれるケースがある。
ある大手企業の内部調査によると、異なる世代同士で「リーダーシップ」について議論した際、ベテラン社員は「自分が責任を取りながらチームを牽引する姿」をリーダーシップとみなした。
一方で若手社員は「チームメンバー一人ひとりの意見を尊重し、役割を分担して進める姿」をリーダーシップだと捉える傾向があったという。
どちらも間違いではないが、この認識の差を放置すれば組織としての一体感が損なわれる恐れがある。
統計的にも、企業内研修において世代間コミュニケーションを課題とする割合が増えている。
2021年の日本経済団体の調査で、企業研修のテーマとして「ダイバーシティとインクルージョン」を挙げる割合が前年比30%増というデータが示された。
ダイバーシティの中にはジェンダーだけではなく、世代間の差も含まれている。
データから見る個人ファンの重要性
ここで別の角度から問題を捉えるため、個人の発信力やファン形成に目を向ける。
世代の違いを乗り越えて「立派だ」と認知される人には、一貫して自分の言葉や行動を持続的に発信し、それを見た人々との間に信頼関係を築く力がある。
言い換えれば、業績や肩書だけでなく、SNSやリアルでのコミュニケーションを通じて「個人ファン」を獲得しているのだ。
あるマーケティング調査(2023年のSNS利用動向レポート)によると、個人のブランディングに成功した人々の多くは、フォロワー数の多寡だけでなく、エンゲージメント率が高いことが判明している。
つまり、単に知名度があるだけでなく、「この人の考え方や行動に共感する」「この人の活動を支援したい」と思われる度合いが高いのが特徴である。
stak, Inc.のCEOという立場で考えるならば、この個人ファンづくりは企業やプロダクトのブランディングとも密接に関わってくる。
世代を超えて多くの支持を得るためには、企業の顔である経営者自身が「百錬成鋼」の精神を体現しつつ、自身の活動や発信を通じて共感を広げる必要がある。
このように「自分の歩みを見せる」スタンスが、SNS世代を含む幅広い層に支持される鍵になると見ている。
もちろん、あまりにも企業色が強すぎる発信は逆効果であり、あくまで個人の考え方に共感を抱いてもらうことが重要である。
まとめ
問題提起に対する結論として、「立派だと感じる人物」は世代や時代背景によって変わるのは当然であり、その多様性を認め合うことが不可欠であるといえる。
多様な価値観の共存を前提としたうえで、百錬成鋼のような「何度でも鍛え上げる姿勢」「挑戦を諦めない精神」はいまだに普遍的な尊敬の源泉として通用している。
数字が示す通り、努力や鍛錬、継続という要素は時代を超えて高い評価を受け続ける傾向にある。
とはいえ、鍛え方や評価の方法は劇的に変化してきた。
かつては軍事教練的な世界で語られた「百錬成鋼」が、現代では起業家やSNSのインフルエンサーが自分の領域を深堀りし、何度も失敗と挑戦を繰り返しながら成功を掴むプロセスに反映されている。
つまり、身体的な鍛錬から頭脳的・創造的な鍛錬へと主軸が移行しているとも言い換えられる。
さらに、企業や社会でも「世代を超えた協業」が急速に進む時代へ突入している。
例えばIoTやAIなど最新テクノロジーを活用するには若い世代の柔軟な発想が必要だが、それを適切にプロジェクト化するには年長者の経験や資金調達の知見が必要になる。
その結果、「この人は立派だ」と尊敬を集める人物は、何らかの専門性と熱意を持ち、それを継続的にシェアしながら、多様なメンバーと協力して成果を出す力を持った人だという認識が広がりつつある。
最終的に、stak, Inc.のような企業が社会に何をもたらせるかも「百錬成鋼」の概念と重ね合わせると見えてくる。
IoTやIT業界では日進月歩で技術が更新されるが、そこで幾度となく試作と改良を繰り返し、より良いプロダクトを創出し続ける姿が評価されるだろう。
実際に世代を超えて好印象を抱かれるには、一貫した鍛錬と情報発信、それを支えるビジョンが必要だ。
ランキングデータや世代別の特徴、そして各種調査から得られる数字が示すように、人々が求める「立派さ」は多様化とともに奥行きを増している。
何が正解かは一概に決められないが、共通するのは「決して歩みを止めない強い意志」と「社会や周囲を動かす発信力」である。
百錬成鋼は、単なる古い精神論ではなく、現代においても各世代がそれぞれのやり方で体現できる普遍的な指針であると結論づける。
【X(旧Twitter)のフォローをお願いします】