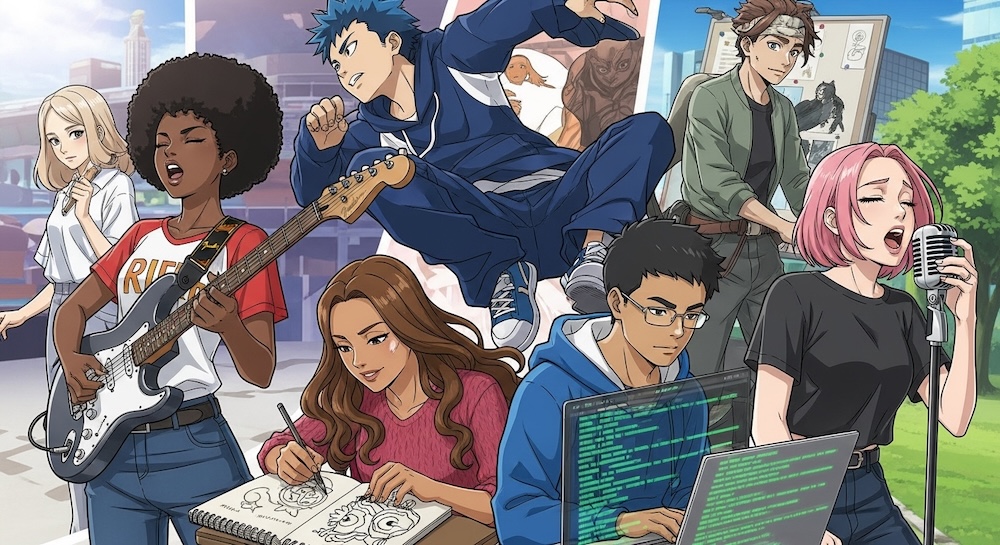百年大計(ひゃくねんのたいけい)
→ 長期的視野に立った大きな計画のこと。
百年大計という言葉は、未来の数十年から百年先を見据えて行う大きな計画を指す概念として定着している。
古くは中国の思想に端を発するといわれており、教育や都市計画など長期的な視点が求められる分野において語り継がれてきた歴史がある。
例えば中国の古典において「十年先を見れば木を植え、百年先を見れば人を育てよ」という趣旨の考え方があるが、そこから転じて「百年かけて取り組むほどの大きな事業や建造物」というイメージが醸成されたと考えられる。
一般的に百年大計が意識されるケースとしては、交通インフラの整備や国土づくり、または産業構造の変革など、大きなスパンを必要とする事業が代表例として挙げられる。
数十年単位で成果が見えない計画は容易には理解されないことも多く、資金調達の困難や人材不足、社会情勢の変動などが複雑に影響し合うため、実現するのが非常に難しい。
だからこそ「百年大計」という響きにはロマンとともに、大きな課題意識が内包されているのが特徴である。
ここでひとつ目に提示したいデータは、経済協力開発機構(OECD)が公表している「インフラ投資に関する長期展望」である。
2020年時点で世界全体のインフラ需要は年間約3.7兆ドルにものぼり、2050年頃にはさらに大きくなる見込みだとされている。
この推計は社会インフラの計画がいかに巨大な経済規模で動いているかを示す好例だが、一方で政治的・経済的に不安定な国や地域では、その計画が百年どころか数年単位すらままならないという現実がある。
ここには「長期的な視野をどれだけ確保できるか」という問題提起が隠れている。
サグラダ・ファミリアの計画思想とガウディの世界
百年大計の象徴的存在として、サグラダ・ファミリアの名は欠かせない。
着工は1882年、当初は別の建築家が設計を担当する予定だったが、後にアントニ・ガウディがプロジェクトを引き継ぎ、誰も見たことがないような壮大な教会建築へと発展していった。
ガウディは自然界に見られる曲線や動植物の構造、光の差し込み方などを徹底的に研究し、斬新なデザインを生み出してきた。
そのデザイン手法は「ガウディ曲線」と呼ばれ、建築史上に残る革命的なアイデアである。
サグラダ・ファミリアは、単に建物の大きさや高さで世界を驚かせてきたわけではない。
むしろガウディの没後も100年以上にわたって工事が継続されるという、壮大すぎる建設期間が注目される理由になっている。
その背景には資金面での制約や戦争による設計図の一部消失、ガウディの構想を正確に再現できる技術が長年確立されなかったことなど、いくつもの要因が積み重なっていた。
興味深いのは、ガウディが「建築とは、時間を味方につける営みだ」というスタンスを持っていたとされる点だ。
実際にガウディは「サグラダ・ファミリアの施主は神であり、神に対して人間の時間は問題にならない」という旨の言葉を残しているという。
この考え方は、物理的な期限の制約を超えたところに価値を見いだすという意味で、まさしく百年大計を地で行く発想といえる。
現在のところ、2026年頃に完成が見込まれているとも言われてきたが、新型コロナウイルスの影響による工事中断で、再度延期の可能性が指摘されている。
サグラダ・ファミリア公式サイトの進捗発表(2022年時点)では塔の一部完成が遅れる見込みであるとされ、完成時期の確定にはまだ不透明な部分が多い。
着工から140年以上を経てもなお未完のまま進む建築は、ガウディの思考がいかに先鋭的かつ長期的な視野に基づいていたかを雄弁に物語っている。
他にもある長期的視野に基づく建造物の事例
サグラダ・ファミリアほど極端なものは少ないが、長期的な視野で着工され、今なおその影響を世界に与え続けている建造物は多い。
例えば、中国の万里の長城が代表的な例として挙げられる。
秦の始皇帝時代(紀元前3世紀)から段階的に建設が始まり、明王朝期(14〜17世紀)に至るまで増改築が繰り返された結果、総延長はおよそ21,196キロメートルにも達すると推計されている(中国国家文物局公表データより)。
その規模は宇宙から確認できる唯一の建造物だと一時期は言われていたほどだが、実際は肉眼で見ることは難しいとされる。
しかし何世紀にもわたり工事が続いたという点で、百年どころか数百年単位の計画と言っていい。
近代的な例では、ブルジュ・ハリファ(アラブ首長国連邦のドバイにある超高層ビル)や、サウジアラビアが計画している「NEOM」と呼ばれる巨大都市構想なども長期的視野をもったプロジェクトである。
特にNEOMは、総投資額が5,000億ドルを超えるとされ、完全に再生可能エネルギーで賄う都市を建設するといった計画だ。
これらは数十年単位でみても異次元のスケールだが、それでもサグラダ・ファミリアほど「完工までに100年を超える」という類の建築とは一線を画す。
興味深いのは、こうした大規模プロジェクトには往々にして技術的なブレイクスルーを伴う点だろう。
サグラダ・ファミリアも初期には存在しなかったコンピューター支援設計(CAD)や3Dプリンターの技術導入によって工期が短縮されてきた経緯がある。
ブルジュ・ハリファも風洞実験や超高強度コンクリートなど革新的技術が多用され、これらが今日の高層建築の標準技術へと進化している。
つまり大きな計画には、それを支えるテクノロジーの成長が不可欠であり、それこそが長いスパンで計画を続ける意義でもある。
ここに、百年大計が持つもうひとつの価値が隠されている。
データに見る具体的な問題
では、こうした百年大計をめぐる最初の問題提起として何があるか。
最も大きいのは、社会の変動にプロジェクト自体が左右される点だろう。
資金調達が困難になったり、世界情勢の変化で計画が滞ったり、労働力の不足で工事が遅延したりする。
サグラダ・ファミリアもスペイン内戦(1936〜1939年)で大きく被害を受け、ガウディのオリジナルの模型や設計図が破壊されたという事実がある。
これだけでも数十年単位の遅れを招く理由としては充分だった。
実際のデータとして、スペイン政府観光局が発表しているバルセロナの年間観光客数は、1980年代には約180万人ほどだったが、2000年代に入ると約700万人、2019年には約1,200万人へ拡大している。
新型コロナの影響はあったものの、再び増加傾向にあるのが現状。観光収入も劇的に上昇しているが、その分だけサグラダ・ファミリアの工事資金が潤沢になったわけではない。
観光客から得られる入場料などは工事のメイン資金源になっている一方で、世界的な経済ショックやパンデミック時の観光客激減で計画に遅れが生じてしまうという皮肉な結果が起きている。
ここには「長期計画でも資金や社会情勢に強靭であるか」という問題が浮き彫りになる。
問題分析と根拠データ
この問題をさらに噛み砕くと、長期視野を重視するプロジェクトほど、資金繰りや社会的支持を得続ける仕組みが必要になる、という点にある。
数十年から百年単位にわたるプロジェクトでは、当初のスポンサーや国のトップが交代してしまうことが当たり前となる。
計画途中で政権が変われば国家予算の配分が変化し、公共事業としての支援が打ち切られる可能性も高い。
さらに民間主導であっても、株主や投資家からのプレッシャーに耐える必要がある。
データ面でも「長期計画の頓挫率」は無視できない。
たとえば、世界銀行が2000年から2020年の間に立ち上げた長期インフラ開発プロジェクト(道路やダムなど)に関する報告によれば、全体の約30%が最終的に計画縮小や中止に追い込まれたという。
背景には不正、腐敗、社会的混乱など複合要因があるが、いずれにしても最初のプラン通りに完遂するのは想像以上に難しい。
サグラダ・ファミリアの場合は、一貫して宗教的意義と観光資源としての魅力が存在し、さらにガウディというカリスマ的人物のブランド力が大きく影響している。
世界遺産に登録された部分もあり、世界的にも保護対象という位置づけが確立されてきた。
こうした継続的な支持があってこそ、140年を超える工事が続いているというのは明らかだ。
裏を返せば、根幹となるコンセプトや社会的意義、ブランド力を維持し続けることができなければ、どれだけ魅力的なプロジェクトであっても百年単位では存続できないということである。
別視点と新たなデータによる深掘り
もう一歩踏み込んで考えると、百年大計が抱えるもうひとつの問題は、技術的な進歩による設計のアップデートが間に合わなくなる可能性だ。
特にAIやIoT、ロボティクスといったテクノロジーが急速に進化している現代では、計画当初の設計思想が数十年後には時代遅れになるケースも十分あり得る。
サグラダ・ファミリアに関して言えば、ガウディのオリジナル設計をいかに忠実に再現するかが重要であり、逆に言えばデザインを大きく変更しないことが価値ともなっている。
ただ実際には、3Dモデルやドローン技術を使った測量など、現代の最先端技術を導入することでガウディの構想をより正確に理解し、実現する流れができつつある。
コンサルティング会社のマッキンゼーが発表した2021年のレポートによると、建設分野への3Dプリンティング技術の導入は今後5年で市場規模が約4倍になると予測され、サグラダ・ファミリアの工事にもさらなる時短が期待されているとの分析もある。
これを別の角度から見ると、テクノロジーの劇的な発展が計画を加速させるという明るい側面もあれば、計画の根底を揺るがすリスクもあるという二面性が浮かび上がる。
たとえば、大規模再生可能エネルギー事業などは、蓄電技術が飛躍的に進歩すれば計画自体を再定義せざるを得ないだろう。
長期計画だからこそ、当初の想定外の技術革新にどう対応するかが問題になるわけだ。
ここには「変化に合わせてアップデートできる柔軟性を百年大計にどう組み込むか」という難題がある。
まとめ
最後に、百年大計にまつわる問題提起とデータを踏まえた上で、結論をまとめる。
まず「社会変動と資金調達のリスク」があるという点。長期間にわたる計画は、政権交代や経済危機、世界的パンデミックなど、想定外の事態に左右されやすい。
サグラダ・ファミリアの工期遅延も、内戦や世界恐慌、疫病の流行など複数の要因が折り重なって生じた結果である。
どれだけ意義深い建築計画でも、資金が途絶えればプロジェクトは止まってしまう。
次に「技術的アップデートの光と影」。3DプリンターやAIといった最新技術の導入によって、サグラダ・ファミリアの工期は当初に比べて格段に短縮された。
マッキンゼーのレポートにも示されるように、建設分野でのデジタル化は加速度的に進むだろう。
それはプロジェクトを円滑にする一方で、当初の設計思想を否定せざるを得ないような大幅な変更を迫る場面も出てくる。
長期計画ならではの難しさといえる。
そして「ブランド力と支持者の存在」。長期的に費用や労力がかかるプロジェクトであればあるほど、社会の支持を得るための説得力や理念が重要になる。
サグラダ・ファミリアにはガウディのカリスマ性、宗教的意義、芸術的価値があるからこそ今なお多くの人が寄付し、訪れ、写真を撮り、発信する。
その総合的な支持が工事の継続を支え、なおかつ新しい技術導入や研究開発の土台ともなっている。
百年大計は決して過去の歴史や宗教施設だけの話ではない。現代の企業経営や社会インフラづくり、さらには個人の人生設計にまで通じる視点である。
日常の中で、5年先や10年先すら見通すのが難しい時代だからこそ、あえて100年後を想像する思考実験が求められているのではないか。
長期的な視野で物事をとらえ、柔軟にアップデートしながら進めていく。そのためには技術や資金の壁を超える覚悟が必要であり、同時に理念や思想を共感してくれる支持者を獲得する努力も欠かせない。
stak, Inc.としても、この発想は企業のプロモーションや採用活動に直結するものと捉えている。
長期的に企業のビジョンを明確に描き、そこに共感した人材や顧客、投資家たちと共に成長していきたい。
そのためには、やはり百年大計という壮大な思考が参考になるし、自らもそうした計画を形にし続ける企業でありたいと強く思う。
サグラダ・ファミリアはこれまで140年以上もの時間をかけて未完の姿を保ち続けてきたが、それ自体がガウディの思想を体現する生きた建築でもある。
そのように、長い時間軸で物事を育て、社会に問いかけ、時代の変遷に耐えられるようアップデートし続けるのが百年大計の本質だと考える。
ここにデータを絡め、現実社会の変化を踏まえてこそ、真に価値のある計画が生まれてくるのではないだろうか。
【X(旧Twitter)のフォローをお願いします】