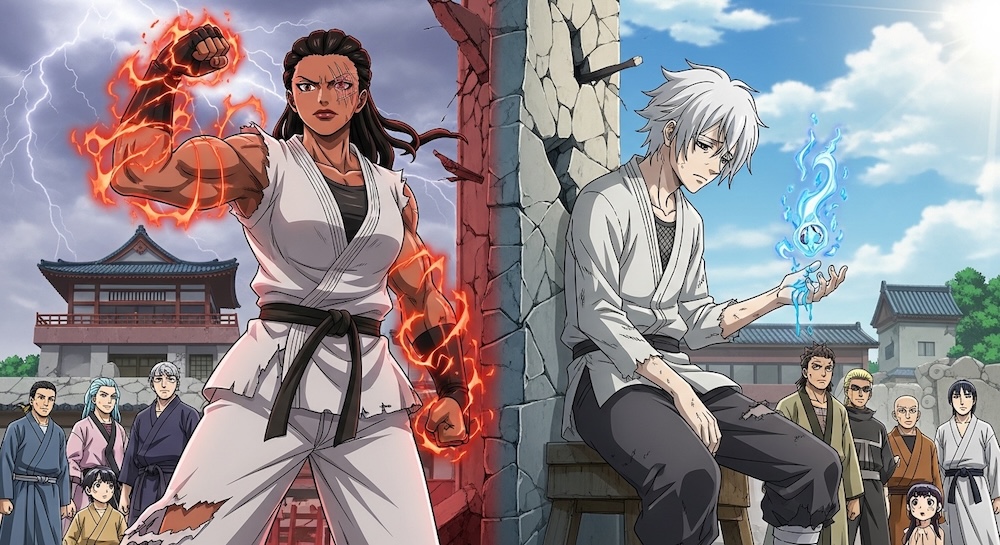罵詈雑言(ばりぞうごん)
→ 汚い言葉で相手をののしること。
罵詈雑言という言葉は、古くは戦国時代や江戸時代などにも存在していたとされる。
人間社会で言葉による攻撃は常にあったわけだが、当時は直接 face-to-face での言い争いがメインだった。
そのため記録に残らないまま朽ちていく罵り合いも数多くあったようだ。
歴史書や文献を見ると、権力者の批判を「落首(らくしゅ)」という形で書きつけたり、芝居や落語で皮肉を交えながら相手を風刺することも多々あった。
「罵詈雑言」という言葉が明確に用いられ始めたのは、江戸期の文献からとされる説もあるが、正確な起源は不明だといわれている。
いずれにせよ人類史のどの時代にも、言葉の暴力というものは存在してきたと考えられる。
近代に入ると、新聞や雑誌といった活字メディアが広がり始め、言葉が目に見える形で大衆に届くようになった。
社会問題を取り扱う際に論説で相手の主張を批判したり、ゴシップ記事でスキャンダルを煽るような表現が用いられたりした。
ここから「言葉による風刺」や「名指しの批判」というものが公の場に明確に記録されるようになった。
明治時代から大正、昭和にかけてメディアの力が増していく過程で、戦争や政治問題に絡んだ批判や中傷が紙面を賑わし、それがきっかけで議論や訴訟が起こるケースも見られた。
ただ、昭和の時代においても個人が誰かを糾弾する場面は限られていた。
大きな権力を批判したい場合、新聞社や雑誌などの編集部を通さなければ大衆に訴えることは難しかったし、テレビに出演するのもごく一部の限られた層だった。
つまり、まだまだ罵詈雑言を自由に発信する手段は限られていたといえる。
ここに大きな転機をもたらしたのがインターネットであり、後にSNSである。
SNS上の罵詈雑言が与える影響
インターネットは人類の歴史において革命的な発明だと言われる。
SNSの普及によって誰もが自由に情報を発信できるようになった結果、個人が持つパワーは格段に拡張された。
ツイートや投稿を通して個人の意見や感情が直接、何千何万もの人々に向けて拡散される。
これは情報民主化において極めて大きな恩恵をもたらした。
一方で、その陰には罵詈雑言が氾濫し、誹謗中傷や差別表現があっという間に拡散されるという負の遺産が生まれた。
SNSでは匿名性やハンドルネームが当たり前のように使われている。
投稿者の身元が特定されにくい環境が、言葉の過激化を加速させる一因だと考えられている。
実名であれば躊躇するような極端な表現も、匿名や仮の名前であれば遠慮なく使われてしまう。
こうした罵詈雑言は、ターゲットを特定して行われる場合もあれば、特定の人種や団体、企業に対して行われるケースもある。
中には純粋な娯楽として乱暴な言葉を投げかける人もいるが、その言葉を受けた相手が精神的に傷つき、深刻な状態に追い込まれることは多くの報道でも取り上げられている。
実際にアメリカの心理学者ジョン・スティーブンスが行った研究(Journal of Cyber Psychology, 2019)によると、SNS上で中傷や誹謗を受けた学生のうち、約43%が不登校傾向や気分障害を訴えるようになったというデータがある。
また、日本でも2019年に明治大学が実施した「SNSとメンタルヘルスに関する調査」で、中高生の約37%が「SNS上の誹謗中傷により気分が落ち込んだ経験がある」と回答している。
これらの数字は、罵詈雑言がいかに大きな影響を持つかを示しているといえる。
名誉毀損と情報開示請求の実態データ
SNSでの罵詈雑言が増加した背景には、スマートフォンの普及と通信インフラの充実が大きく寄与している。
総務省の「令和4年度情報通信白書」によると、スマートフォンの保有率は国民全体で80%を超え、SNSの利用率は約70%にまで達している。
こうした状況下で、個人が個人に向けて言葉を投げかける機会が爆発的に増えたわけだ。
このような罵詈雑言の増加に伴い、名誉毀損や侮辱罪などでの訴え、そして投稿者の情報開示請求も急増している。
法務省が公表している「インターネット上の名誉毀損・侮辱に関する統計」(2020年度版)によれば、インターネット上の名誉毀損・侮辱に関して検挙に至った件数は2015年から2020年の5年間で約1.8倍に増えている。
また、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報の開示請求件数も、2017年から2021年の間に約2倍近く増加しているとのデータがある(総務省・プロバイダ責任制限法関連データ、2021年版)。
こうした情報開示請求の流れとしては、まず被害者が弁護士に相談し、該当するSNS運営会社(Twitter社やMeta社など)に対して加害者のIPアドレスや接続情報の開示請求を行う。
その後、プロバイダや携帯キャリアに対して開示を求め、最終的に個人が特定されるというステップが一般的だ。
かつてはこうした手続きが時間や手間、費用もかかるため、泣き寝入りするケースも多かった。
しかし近年は手続きの簡略化や弁護士費用のハードル低下などにより、名誉毀損や誹謗中傷に対して法的措置を取る動きが活発化している。
実際にTwitter社(現X社)が公開した2020年度の「Transparency Report」においても、日本からの情報開示請求件数は世界全体の約2割を占めており、その割合は年々増加傾向にある。
国際的にも日本はSNSの名誉毀損や誹謗中傷への法的対応が多い国の一つと言われている。
背景として、法制度が整備されていないというわけではなく、問題が表面化しやすい国民気質や企業のブランドイメージを重視する傾向などが考えられる。
世界各国のルールと日本の遅れ
こうしたSNS上の罵詈雑言や誹謗中傷に対して、国ごとに対応策が異なる。
アメリカは言論の自由を非常に重視するため、よほど明確な被害が証明されない限りは法的措置が難しい面がある。
一方で、ドイツでは「Netzwerkdurchsetzungsgesetz(通称ネットワーク強制法)」という法律が2017年に施行され、SNS運営会社に対して違法コンテンツの迅速な削除や対応を義務づけている。
違反した場合には高額な罰金が科せられるため、各社は対応マニュアルを整備して積極的に投稿削除やアカウント凍結を行っている。
イギリスやフランスでも似たような法整備が進んでおり、個人が深刻な誹謗中傷にさらされた場合は警察当局が積極的に動く事例が増えている。
欧州連合(EU)ではGDPR(一般データ保護規則)に準じたかたちで、個人情報の保護と同時に誹謗中傷を行う発信者の特定や処罰を柔軟にできる体制が作られつつある。
こうした動きに比べると、日本の法整備はやや出遅れているという指摘が多い。
もちろん、プロバイダ責任制限法や侮辱罪の厳罰化などの動きは見られるが、スピードや運用面での実効性がまだ追いついていないのが現状だ。
この差は、単に法制度の問題だけではない。社会的・文化的背景も大きく影響する。
例えばドイツのようにヘイトスピーチを徹底的に排除しようとする歴史的経緯がある国では、法規制への国民の支持が高い。
一方、日本は「表現の自由」を重んじる理念と「相手に直接文句を言いづらい」風習が入り交じっていて、根本的な意識改革が進みにくいとの分析がある。
それが結果的に、他国に比べて整備が遅れる一因になっていると考えられている。
社会変革とこれからの展望
日本でも政府や民間が中心となり、インターネット上の罵詈雑言に対する対策が活発化している。
具体的には、プロバイダ責任制限法の改正や侮辱罪の厳罰化、さらにSNS事業者への監督強化などが挙げられる。
法的措置だけでなく、教育や啓発活動の面でもSNSリテラシーを高めようとする取り組みが進められている。
小中学校における情報モラル教育の充実や、民間団体によるSNS研修セミナーの開催が増えてきた。
そうした動きの背景には、罵詈雑言が社会全体のブランディングや国際的信用にも影響すると認識され始めている点がある。
企業経営の観点でも、SNSで自社や自社製品が誹謗中傷の対象になるリスクは無視できない。
もし放置すればブランドイメージが大きく損なわれかねない。
だからこそ、企業はSNSでの監視体制を整え、誤った情報の拡散や過激な罵りがあった場合には訂正や法的措置を適切に行う必要がある。
カスタマーサポートやカスタマーリレーションの一環として、SNSでの対応を最適化する取り組みも広がりつつある。
さらに、AIによる自然言語処理を活用して、誹謗中傷や差別表現を自動的に検知・遮断するシステムを開発する企業も登場している。
これは「AI×クリエイティブ」という新たなビジネスチャンスを生むきっかけにもなる。
個人の立場からみても、ネット上の誹謗中傷を放置することは将来の就職やキャリア、プライベートにも悪影響を及ぼす可能性がある。
すでに欧米ではSNSアカウントを調べて不適切な投稿があれば採用を取りやめる企業も珍しくない。
そのため、「ネットリテラシー教育」や「情報保護教育」がこれまで以上に重要とされる流れになっている。
今後は、ITやIoTを駆使したシステムで投稿をモニタリングし、トラブル発生前に未然に防ぐサービスが主流になっていく可能性が高い。
IT・AI・IoT・クリエイティブの観点から見る可能性
罵詈雑言への対策としてITやAIの活用は不可欠とされている。
SNS上の投稿を監視し、特定のキーワードや文脈を判断して「これは誹謗中傷にあたるかもしれない」と自動検知する仕組みは既に多くのプラットフォームで導入されている。
例えばMeta社は独自のAIシステムを複数導入しており、差別的表現や誹謗中傷を含む投稿を短時間で自動削除する機能を強化している。
Twitter社(現X社)も類似のシステムを活用し、24時間体制でコンテンツをチェックしている。
これらのAIシステムはまだ完璧ではないが、日々アップデートされており、精度向上が期待される。
一方で、AIが投稿内容を誤って「罵詈雑言」や「誹謗中傷」と判定してしまうリスクも残る。
この誤判定によって正当な批判や言論がブロックされる恐れもある。
そのため、クリエイティブな視点から「健全な表現の自由」と「他者を傷つけない言葉の使い方」のバランスを探る研究やプロジェクトも多数進められている。
たとえば、イギリスの大学機関が開発している「Contextual AI Filter」は、投稿の前後関係を学習して、皮肉やジョークのようなグレーゾーンの判定精度を高める試みを行っているとの報告がある(University of London, 2021年研究発表)。
IoTとの連携でユニークな事例が注目を集めることもある。
たとえば、子どものスマートデバイス上で誹謗中傷のキーワードが一定数検知された場合に、親や教師へ自動的に通知が届く仕組みを提供するサービスが海外でスタートしている。
日本国内でもこうしたIoT機器の導入が広がれば、子どもをターゲットにしたSNS上の罵詈雑言を早期発見して対策を打つことが可能になるはずだ。
さらに、音声SNSやバーチャル空間においても悪質な発言を検知してフィルタリングする技術が研究されている。
今後はこうしたイノベーションを支えるエンジニアリングも盛り上がっていくと期待される。
「攻撃的な言葉を取り締まる」という発想だけでなく、もっと建設的なコミュニケーションを促すクリエイティブな施策も増えている。
あるSNSでは相手を批判する投稿をする際、システムが「本当にこの表現で投稿するのか」というワンクッションを設ける取り組みを実施した。
結果として罵詈雑言を含む投稿が約15%減ったというデータもある(特定SNS社内統計、2022年)。これはユーザーに再考を促すだけで言葉の過激化をある程度抑制できる証拠だといえる。
エビデンスとして、他国の成功事例を参考にする企業や自治体が増えている。
上述したドイツのネットワーク強制法をはじめ、イギリスで進められている「Online Safety Bill」、フランスの「Avia法」などの動向に注目すれば、日本でもさらに新しいルール制定や企業独自のガイドラインを整備する動きが強まる可能性がある。
IT・AI・IoT領域のイノベーションは罵詈雑言対策においても重要な役割を果たし、同時に新たなビジネスチャンスを呼び込む可能性を秘めているといえそうだ。
まとめ
罵詈雑言という行為は、古くから存在してきた人間の負の一面でもある。
それがSNSの発展とともに、地球規模で拡散されるようになり、その影響力も増してきた。
名誉毀損や情報開示請求の増加は、人々が罵詈雑言にさらされる機会が格段に増えた一方で、「泣き寝入りしなくても法的手段がある」という認識が広がった証拠でもある。
社会全体としては、よりクリーンなオンライン環境を作ろうとする動きが進んでいるものの、法整備や教育の面では依然として課題が山積しているといわざるを得ない。
一方で、罵詈雑言への対処はトラブル回避という消極的な側面だけでなく、経営やクリエイティブな観点で捉えれば新たなイノベーションの可能性を生み出し得る。
AIによる不適切表現の検知や、IoTを使ったリアルタイムの監視システム、さらに「投稿前にユーザーに再考を促す」UI設計など、クリエイティブな視点を導入すれば社会をよりポジティブな方向に変えることは可能だ。
企業のブランディングやマーケティングでも、ユーザーや顧客と良好なコミュニケーションを築くためのノウハウがこれからますます求められる。
罵詈雑言が生み出す深刻な問題を契機に、ネット上の言葉遣いを再考する潮流をどう事業に生かすかが、これからのカギを握るはずだ。
個人的な意見としては、IT・AI・IoTを活用した対策は確かに有効だが、根本にあるのは「人同士が尊重し合う姿勢」であり、それなしにはいくら法整備や技術開発を進めても限界があると考えている。
教育現場ではSNSリテラシーや言葉の力を正しく理解させるプログラムを拡充し、企業ではCSR活動やブランドイメージ構築の一環として「オンラインコミュニケーションのガイドライン」を設けることが必要だと感じる。
SNSをはじめとしたインターネットの革命的メリットを活かしつつ、負の側面を減らすことができれば、より豊かな情報社会が実現されるはずだ。
罵詈雑言は無くならないという悲観的な見方もあるが、人間の歴史を振り返れば、ネガティブな行動や言動が完全に消えることは確かにない。
しかし、それを最小限に抑え、言葉の力を健全な方向へと導く仕組みを作ることは可能だと信じている。
インターネットとSNSの普及は人類にとって大きな躍進だが、同時に罵詈雑言に代表される課題も顕在化した。
だからこそ、経営やIT、AI、IoT、クリエイティブ、エンタメ、PR、ブランディング、マーケティングの知見を総合的に活かして問題解決へ導く価値がある。
そこに stak, Inc.のような機能拡張型のIoTを手がける企業が参入すれば、より洗練された仕組みが生まれる可能性は十分にあるだろう。
目指すべきは、テクノロジーと人間の倫理観が融合し、オンライン上でもオフラインと同様にお互いをリスペクトできる社会の実現だ。
全ての人が安心して発言できるインターネット空間は、必ずしも夢物語ではない。
ルール整備の遅れを指摘される日本においても、世界の事例を参考にしつつ独自の発想やテクノロジーを取り入れ、ネットコミュニケーションをアップデートしていく道筋は十分にあると感じている。
【X(旧Twitter)のフォローをお願いします】