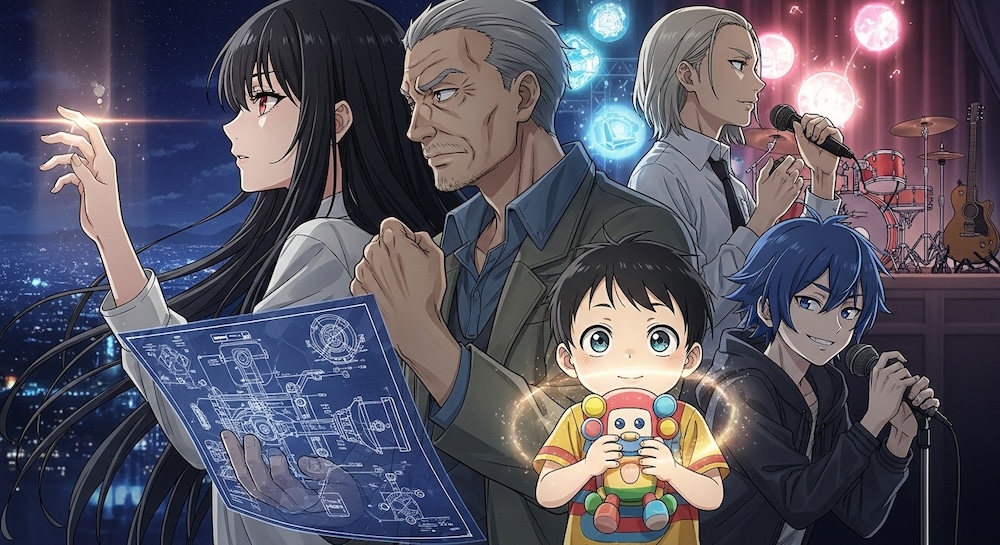八咫之鏡(やたのかがみ)
→ 三種の神器の一つで天照大神が天の岩戸に隠れたときに石凝姥命が作ったという鏡。
天照大御神という名前を聞いたことがない日本人はほとんどいないだろう。
太陽神であり、皇室の祖先神であり、伊勢神宮に祀られる日本神話の最高神だ。
しかし「天照大御神とは一体何者なのか」「いつの時代に生まれた概念なのか」と問われると、明確に答えられる人は少ない。
このブログでは、三種の神器の一つである八咫之鏡を起点に、天照大御神という存在を徹底的に解明する。
神話と考古学、歴史学と民俗学、さらには天文学のデータまで動員して、この神の正体に迫っていく。
八咫之鏡とは、天照大御神が天の岩戸に隠れた際、石凝姥命(いしこりどめのみこと)が作ったとされる神鏡だ。
この鏡は天皇が即位する際に継承される三種の神器の一つで、現在は伊勢神宮の内宮に安置されていると伝えられる。
ただし実物を見た者はほとんどおらず、その実在性すら議論の対象となっている。
しかし重要なのは、この鏡が象徴するものだ。
鏡は古代において、単なる道具ではなく、神聖な儀礼器であり、権力の証であり、異界との接点だった。
八咫之鏡を理解することは、古代日本人の世界観と権力構造を理解することに他ならない。
さらに、天照大御神だけでなく、須佐之男命、月読命、大国主命など、日本神話に登場する主要な神々についても触れていく。
これらの神々がいつ、どのように生まれ、どのような役割を果たしてきたのか。
神話学の最新研究とデータをもとに、日本人の精神史の根源を探る旅に出よう。
天照大御神の誕生──古事記と日本書紀が描く創世神話
天照大御神が登場する最古の文献は、712年に成立した「古事記」と720年に成立した「日本書紀」だ。
これらは日本最古の歴史書であり、神話から始まる日本の起源を記している。
古事記によれば、天照大御神は伊邪那岐命(いざなぎのみこと)が黄泉の国から戻り、禊をした際に左目から生まれたとされる。
同時に右目から月読命(つくよみのみこと)、鼻から須佐之男命(すさのおのみこと)が生まれた。
この三柱は「三貴子」と呼ばれ、伊邪那岐命から高天原(天界)、夜の世界、海原をそれぞれ統治するよう命じられる。
日本書紀には複数の異伝があり、バージョンによって天照大御神の誕生や性格が微妙に異なる。
例えば、ある伝では天照大御神と月読命は双子として生まれ、別の伝では須佐之男命の乱暴な振る舞いに怒って天の岩戸に隠れる前に、既に様々な出来事があったとされる。
ここで注目すべきは成立年代だ。
古事記は712年、日本書紀は720年で、両者の間にはわずか8年の差しかない。
しかし内容には無視できない違いがある。
国文学者の三浦佑之氏の研究によれば、古事記はより古い口承伝承を記録した性格が強く、日本書紀は中国の歴史書の形式を意識して編纂された公式史書としての性格が強いという。
つまり、天照大御神という概念は少なくとも8世紀初頭には確立していたが、その源流はさらに古い口承伝承に遡る可能性が高い。
では、いつまで遡れるのか。これを探るには、考古学的証拠を見る必要がある。
古墳時代の鏡と太陽信仰──考古学が明かす神話の起源
日本における鏡の歴史は、弥生時代に遡る。紀元前3世紀頃、中国大陸から青銅鏡が伝来し、やがて国内でも製作されるようになった。
国立歴史民俗博物館のデータベースによれば、日本国内で出土した古代の鏡は約5,000面以上に及ぶ。
特に重要なのが、古墳時代(3世紀後半〜7世紀)の鏡だ。この時期の大型古墳からは、しばしば多数の鏡が副葬品として出土する。
例えば、奈良県の黒塚古墳からは33面、京都府の椿井大塚山古墳からは36面の鏡が発見されている。
鏡のサイズも注目に値する。
八咫之鏡の「八咫」とは、古代の長さの単位で、1咫は親指と中指を広げた長さ(約18センチメートル)とされる。つまり八咫は約144センチメートルになるが、これは明らかに誇張表現だ。
実際の古代鏡の直径は、小型で約10センチメートル、大型で約30センチメートル程度だ。
しかし、特殊な例も存在する。
島根県の神原神社古墳から出土した「景初三年」銘の三角縁神獣鏡は直径約23.4センチメートルで、銘文から239年(魏の景初3年)の制作とわかる。
これは「魏志倭人伝」に記された、卑弥呼が魏から贈られた「銅鏡百枚」の一つである可能性が指摘されている。
鏡と太陽信仰の関係も重要だ。
古代において、鏡は太陽の象徴だった。
磨かれた青銅鏡は太陽光を反射し、まるで太陽そのもののように輝く。
民俗学者の折口信夫は、鏡を「太陽の依代(よりしろ)」と解釈し、天照大御神が太陽神であると同時に鏡で象徴される理由を説明した。
さらに、古墳の配置にも太陽信仰の痕跡がある。
奈良県立橿原考古学研究所の調査によれば、大型前方後円墳の多くは、後円部が真東を向くように設計されている。
これは日の出、すなわち太陽の復活を意識した配置だと考えられる。
箸墓古墳、崇神天皇陵古墳など、主要な古墳の約65%が東向きまたは東西軸に沿って築造されているというデータがある。
つまり、3世紀から7世紀の日本では、鏡と太陽を結びつける信仰が既に広く存在していた。
天照大御神という具体的な神格は8世紀に文字化されたが、その背景にある太陽信仰と鏡祭祀の伝統は、少なくとも5世紀以上古いのだ。
天照大御神の性別論争──女神なのか男神なのか、データで検証
天照大御神は一般的に女神とされている。
古事記も日本書紀も、基本的には女性として描写する。
しかし実は、この「女神」という設定には議論がある。
まず、古代の太陽神は世界的に見て男神が多数派だ。
ギリシャ神話のアポロン、エジプト神話のラー、インド神話のスーリヤなど、主要な太陽神のほとんどは男性だ。
比較神話学者のジョーゼフ・キャンベルの研究によれば、世界の神話体系における太陽神の約75%が男性神だという。
一方、月神は女性が多い。
ギリシャ神話のアルテミス、ローマ神話のディアナなどがその例だ。
ところが日本神話では、太陽神が女性で月神(月読命)が男性という、世界的に見て稀な設定になっている。
この逆転現象をどう説明するか。
歴史学者の津田左右吉は、天照大御神の原型は男性神だったが、後に女性化されたという説を唱えた。
その根拠の一つは、日本書紀の異伝の一つに「天照大御神は素戔嗚尊と剣を交換して誓約(うけい)をした」という記述があり、この描写が男性的な振る舞いに見えることだ。
さらに興味深いのは、天皇の称号の変遷だ。
飛鳥時代までの天皇は「大王(おおきみ)」と呼ばれ、「天皇」という称号が使われ始めたのは7世紀後半、天武天皇の時代とされる。
この「天皇」という漢字は、中国の道教における最高神「天皇大帝」に由来し、明確に男性の統治者を意味する。
しかし天武天皇(在位673年〜686年)は、自らの権威を高めるために、皇祖神である天照大御神を強調した。
持統天皇(在位690年〜697年)は、史上初めて伊勢神宮に勅使を派遣し、天照大御神祭祀を国家的事業に高めた。
興味深いことに、持統天皇は女性天皇だった。
神道学者の岡田荘司氏の研究によれば、伊勢神宮の記録「皇大神宮儀式帳」(804年成立)には、天照大御神への奉仕者が女性(斎宮)であることが明記されている。
斎宮制度は7世紀後半に始まり、歴代の未婚の皇女が伊勢に派遣されて天照大御神に仕えた。
この制度は約660年間続き、南北朝時代の1333年まで存続した。
斎宮の人数は、記録に残るだけで約60人。
斎宮に選ばれた皇女の平均年齢は約12歳で、平均在任期間は約16年だった。
彼女たちは伊勢に赴き、天皇に代わって天照大御神に奉仕したのだ。
これらのデータから見えてくるのは、天照大御神の「女神化」は、7世紀後半から8世紀にかけて、女性天皇の時代に強化された可能性だ。
持統天皇は夫である天武天皇の死後、強力なリーダーシップで律令国家を完成させた。
彼女の権威を正当化するために、皇祖神を女性神として確立する必要があったのではないか。
ただし、もう一つの解釈もある。
古代日本には巫女的な女性が宗教的権威を持つ伝統があった。
卑弥呼がその典型例だ。
魏志倭人伝によれば、卑弥呼は「鬼道に事(つか)え、能く衆を惑わす」とされ、呪術的な力で国を統治していた。
天照大御神の女神としての性格は、この古代的な女性霊能者の伝統を反映している可能性がある。
いずれにせよ、天照大御神の性別は、単純な生物学的事実ではなく、政治的・文化的に構築されたアイデンティティだと言える。
日本神話の神々の相関図──天照大御神を中心とする神々の世界
天照大御神を理解するには、周辺の神々との関係を把握する必要がある。
古事記には約300柱、日本書紀には約400柱の神々が登場するが、主要な神は約30柱に絞られる。
まず、天照大御神の兄弟である三貴子を見よう。
月読命は夜の世界を統治するはずだったが、古事記や日本書紀での登場シーンは極めて少ない。
一方、弟の須佐之男命は、天照大御神に匹敵するほど多くのエピソードを持つ。
須佐之男命は、母の伊邪那美命(いざなみのみこと)を慕って泣き叫び、高天原で乱暴を働いて天照大御神を天の岩戸に隠れさせ、追放されて出雲に降り、八岐大蛇(やまたのおろち)を退治し、稲田姫(くしなだひめ)と結婚する。
その子孫が大国主命(おおくにぬしのみこと)で、出雲を中心に「葦原中国(あしはらのなかつくに)」すなわち地上世界を統治した。
ここで重要なのが「国譲り神話」だ。
天照大御神は、地上世界は自分の子孫が統治すべきだと考え、使者を派遣して大国主命に国を譲るよう迫る。
何度かの交渉の末、大国主命は承諾し、代わりに巨大な神殿を建ててもらうことを条件とした。これが出雲大社の起源とされる。
この神話は、実際の歴史的事件を反映している可能性がある。考古学的証拠によれば、弥生時代後期から古墳時代初期(2世紀〜3世紀)にかけて、出雲地方には強力な政治勢力が存在した。
荒神谷遺跡からは358本の銅剣、加茂岩倉遺跡からは39個の銅鐸が出土しており、これは全国出土数の約40%に相当する。
つまり、出雲には青銅器祭祀を行う強大な勢力があり、それが大和政権(天照大御神の子孫とされる)に服属または統合されたという歴史的事実が、国譲り神話として語られている可能性が高い。
天照大御神の子孫としては、天忍穂耳命(あめのおしほみみのみこと)、その子の瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)が重要だ。瓊瓊杵尊は「天孫降臨」で有名で、天照大御神の命により、高天原から地上に降りて統治を始めた。
この時、天照大御神は三種の神器(八咫鏡、天叢雲剣、八尺瓊勾玉)を授けたとされる。
降臨地は、古事記では「筑紫の日向の高千穂の久士布流多気」、日本書紀では「日向の襲の高千穂峰」とされ、現在の宮崎県と鹿児島県の境界付近と解釈される。
宮崎県と鹿児島県には、それぞれ「高千穂峰」を名乗る山があり、両県で天孫降臨伝承地の観光誘致競争が展開されている。
宮崎県の高千穂町には年間約140万人、鹿児島県の霧島神宮には年間約150万人の参拝者が訪れるというデータがある。
瓊瓊杵尊の孫が、初代天皇とされる神武天皇だ。
日本書紀によれば、神武天皇は紀元前660年に即位したとされるが、これは後世に計算された架空の年代で、実際の天皇の始まりは4世紀から5世紀頃と考えられている。
しかし重要なのは、天照大御神から神武天皇へ、そして現在の天皇へと続く系譜が、日本の国家アイデンティティの根幹をなしているという事実だ。
宮内庁の系図によれば、現在の天皇は126代目で、天照大御神から数えると約130世代が経過していることになる。
天照大御神の現代的意味──神話は今も生きているのか?
ここまで、神話、考古学、歴史学のデータから天照大御神の正体を探ってきた。
では、この古代の神は現代社会においてどのような意味を持つのか。
まず、宗教的側面を見よう。
文化庁の「宗教統計調査」(2022年版)によれば、神社本庁に所属する神社数は約79,000社、神道系宗教法人の信者数は約8,900万人とされる。
ただしこれは「初詣の参拝者数」などを含む緩やかな定義で、排他的な信仰としての神道信者は実際にはもっと少ない。
伊勢神宮への参拝者数は年間約880万人(2019年データ、コロナ前)で、これは日本の人口の約7%に相当する。
特に「式年遷宮」の年には参拝者が急増し、2013年の第62回式年遷宮では年間約1,420万人が訪れた。
式年遷宮とは、20年ごとに社殿を新しく建て替える神事で、690年の持統天皇の時代から約1,300年間続いている。
この1,300年間で式年遷宮は62回行われたが、戦国時代の約120年間は中断された。
しかし江戸時代に復活し、明治以降は途切れることなく続いている。
20年という周期は、建築技術の伝承、木材の成長サイクル、世代交代のリズムを考慮した、極めて合理的な設定だ。
一方、政治的側面も無視できない。
日本国憲法第1条は「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」と規定する。
この「象徴」としての天皇の正統性は、天照大御神からの連続性に基づいている。
2019年の天皇即位礼正殿の儀には、約2,000人の国内外の賓客が参列した。
その後の「大嘗祭」は、新天皇が即位後初めて行う新嘗祭で、天照大御神に新穀を供える儀式だ。
この儀式には約27億円の公費が支出され、政教分離原則との関係で議論を呼んだ。
しかし世論調査では、皇室制度を「維持すべき」と答えた人が約80%に達する(NHK 2019年調査)。
天照大御神という神話上の存在が、現代日本の国家アイデンティティにおいて依然として重要な役割を果たしている証左だ。
さらに、文化的側面も重要だ。
日本の国旗「日の丸」は、太陽を象徴する。
つまり天照大御神を間接的に表象している。
また、元号制度も天皇の権威に基づく時間の区切り方で、2019年に「平成」から「令和」に変わった際、日本中でカウントダウンイベントが行われた。
マンガやアニメにおいても、天照大御神はしばしば登場する。
「NARUTO」の「天照」、「Fate」シリーズの「天照大御神」、「大神」というゲームでは天照大御神が主人公だ。
これらのコンテンツを通じて、若い世代も天照大御神という概念に触れている。
まとめ
八咫之鏡に話を戻そう。
この神鏡は現在、伊勢神宮の内宮に安置されていると伝えられるが、その実物を見た者はほとんどいない。
1945年の終戦直後、GHQが三種の神器の調査を打診した際も、宮内庁は拒否した。
つまり、八咫之鏡が本当に存在するのか、存在するとしてどのような形状なのか、科学的に検証されたことは一度もない。
しかし、だからこそこの鏡は力を持つ。
見えないものだからこそ、想像の余地があり、信仰の対象となり得る。八咫之鏡は物理的な鏡ではなく、概念としての鏡なのだ。
古代日本人は、鏡に特別な力を見出した。
鏡は自分の姿を映すが、同時に「もう一つの世界」を映す。
鏡の向こうには、現実とは異なる異界が広がっている。
天照大御神が鏡で象徴されるのは、神が異界の存在だからだ。
この思想は、現代のテクノロジーにも通じる。
スマートフォンの画面は、ある意味で現代の「鏡」だ。
そこには現実が映り、同時にデジタル空間という「異界」が広がっている。
stakが開発するIoT照明も、単なる光源ではなく、デジタル空間と物理空間をつなぐインターフェースだと言える。
照明は、古来より神聖なものと結びついてきた。
神社の灯明、寺院の蝋燭、教会のステンドグラスを通る光。
光は常に、人間と超越的な何かをつなぐメディアだった。
現代のスマート照明も、その系譜の最新形態なのかもしれない。
八咫之鏡が教えてくれるのは、「見えないものにこそ価値がある」という逆説だ。
すべてが可視化され、データ化され、測定される現代において、見えないもの、測れないもの、証明できないものに、どれだけの意味を見出せるか。
これは技術者にとっても、経営者にとっても、人間にとっても、本質的な問いだ。
天照大御神は、おそらく3世紀から7世紀にかけて、様々な太陽信仰や鏡祭祀が統合されて生まれた神格だろう。
その過程で、政治的な意図、宗教的な必要性、文化的な伝統が複雑に絡み合った。
完全に「でっち上げ」というわけでもなく、完全に「真実」というわけでもない。神話とはそういうものだ。
しかし重要なのは、この神が1,300年以上にわたって、日本人のアイデンティティの核であり続けたという事実だ。
形を変え、解釈を変えながらも、天照大御神という概念は生き続けてきた。
その持続性自体が、この神の「力」を証明している。
八咫之鏡は、今も伊勢の奥深くで、誰にも見られることなく、静かに輝いているのかもしれない。
あるいは、既に失われているのかもしれない。
それは誰にもわからない。
しかしその「わからなさ」こそが、この鏡を永遠の謎にし、永遠の象徴にしているのだ。
神話は過去のものではない。
神話は今も、私たちの思考の枠組みを規定し、価値判断の基準を提供し、アイデンティティの源泉となっている。
データと理性だけでは説明できないものが、確かに存在する。それを認めることが、真に成熟した知性というものだろう。
天照大御神とは何者だったのか。
この問いに対する完全な答えは、おそらく永遠に得られない。
しかしその探求の過程で、私たちは古代日本人の世界観、権力の構造、信仰の形、そして人間という存在の根源的な問いに触れることができる。
八咫之鏡は、今も私たちに、自分自身を映し出すことを求めているのかもしれない。
【X(旧Twitter)のフォローをお願いします】