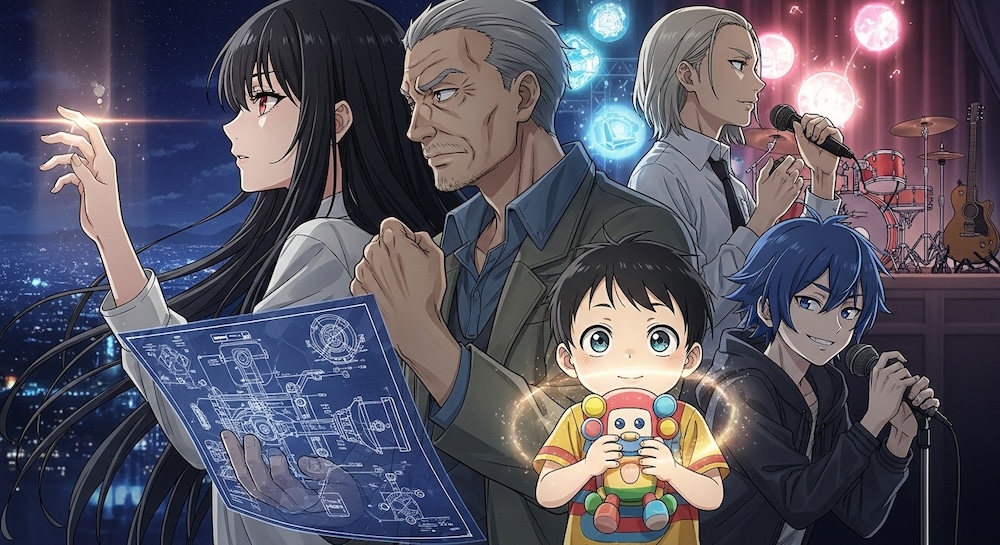薬石無効(やくせきむこう)
→ 薬や治療も効きめがなく、手当ての甲斐がないこと。
薬石無効(やくせきむこう)は、唐の第16代皇帝・宣宗(847年〜859年在位)が自らの病の重篤さを告げ、皇太子への即位を命じた冊文の中で使用された言葉だ。
「薬石、功無し」と訓読され、あらゆる薬や治療を施しても効き目がなく、手を尽くした甲斐なく死に至ることを意味する。
「薬石」の「薬」は薬草を、「石」は石鍼(いしばり)と呼ばれる治療用の石製の鍼を指す。
転じて、医療全般を表す言葉となった。
唐の宣宗が遺した冊文には「薬石効なく、弥留(ビリュウ)斯(ここ)に迫れり」とあり、重病から抜け出せなくなった絶望的な状況が記されている。
この言葉が生まれた9世紀の唐代、医療は現代と比較にならないほど限られていた。
感染症、外傷、内臓疾患など、今日では容易に治療できる病気の多くが致命的だった。
しかし、それから約1,200年が経過した現在、医学と薬学は驚異的な進化を遂げている。
かつて「薬石無効」とされた数多くの疾患が、今や恐れるに足らない病となった。
本記事では、人類が薬をいつから使い始めたのか、そして医学と薬学がどのように進化してきたのかを、考古学的証拠と統計データに基づいて詳細に解き明かしていく。
このブログで学べる薬と医療の驚異的進化の全貌
本記事は、人類最古の薬の使用から現代医療に至るまでの壮大な歴史を、確固たるエビデンスとデータで辿る。
単なる歴史の羅列ではなく、各時代における医学的ブレイクスルーが人類の寿命と生活にどれほど劇的な影響を与えたかを、数値で示していく。
薬の歴史は人類史そのものと言っても過言ではない。
約5万年前のネアンデルタール人の遺跡からは、薬用植物と考えられるシダ植物の成分が発見されている。
これは人類最古の薬の使用例の可能性がある。
日本でも、1万数千年前の縄文時代の住居跡からキハダ(黄柏)が発見されており、薬として使用されていたと推測されている。
文字による記録が残る最古の薬学書は、紀元前3000年頃のメソポタミア地域でシュメール人が粘土板に記した処方だ。
紀元前1550年頃のエジプトでは、約700種の薬品が記録された「エーベルス・パピルス」が作成されている。
しかし、医学が真に科学的なアプローチを取り始めたのは、紀元前400年頃のギリシャで「医学の父」ヒポクラテスが登場してからだ。
それまでの祈祷中心の医療から、病気の原因を追求する姿勢へと転換した。
本記事では特に、以下の革命的な医学的発見に焦点を当てる。
第一に、1796年のエドワード・ジェンナーによる種痘の発明。
第二に、1928年のアレクサンダー・フレミングによるペニシリンの発見。
第三に、1803年の華岡青洲による全身麻酔手術の成功。
これらの発見が人類の平均寿命をどれほど延ばしたかを、具体的な数値で検証していく。
かつて致命的だった病気とデータで見る医療前史の過酷さ
現代に生きる私たちにとって、風邪や軽い怪我で命を落とすことは想像しがたい。
しかし、医学が発達する以前の人類にとって、今日では些細な病気が死を意味していた。
その過酷な現実をデータが如実に示している。
平均寿命の歴史的変遷を見ると、医療の進歩がいかに劇的だったかがわかる。
日本の明治期(1891年〜1898年)の平均寿命は、男性が42.8歳、女性が44.3歳だった。
当時は就労人口の約70%が農業に従事し、近代医療制度の普及は極めて限定的だった。
60年後の1955年になっても、平均寿命は男性63.6歳、女性67.8歳にとどまっていた。
さらに60年後の2015年では男性80.8歳、女性87.0歳となり、この120年間で男女ともに約40年も平均寿命が延びた計算だ。
2024年の最新データでは、男性81.09歳、女性87.13歳に達している。
この平均寿命の延伸に最も貢献したのが、乳児死亡率の劇的な減少だ。
明治期から昭和初期にかけて、乳児死亡率(出生1,000人あたりの1歳未満の死亡数)は150〜200という高い水準だった。
これは、生まれた赤ちゃんの15〜20%が1歳を迎える前に亡くなっていたことを意味する。
戦後の1947年、日本にペニシリンが普及し始めた年の乳児死亡率は76.7だった。
それが1960年には30.7、1980年には7.5、2000年には3.2、そして2022年には1.8にまで低下している。
約75年間で、乳児死亡率は40分の1以下になった。
感染症による死亡も凄まじかった。
日本における天然痘の記録を見ると、明治時代には年間2万人から7万人の患者が発生する規模の流行が6回発生している。
第二次世界大戦後の1946年にも約18,000人の患者が発生し、約3,000人が死亡した。
天然痘の致死率は約20〜30%で、生存者の多くに深刻な瘢痕が残った。
結核も「国民病」「亡国病」と呼ばれるほど猛威を振るった。
厚生労働省の統計によれば、1950年の結核による死亡者数は年間約12万人で、全死亡者の約14.2%を占めていた。
1947年に結核予防法が施行され、BCGワクチンの普及と抗結核薬ストレプトマイシンの導入により、結核死亡率は急速に低下。
2022年の結核死亡者数は約1,900人となり、70年間で約98%減少した。
肺炎も主要な死因だった。
戦前の日本では、肺炎は死因の上位を占め続けていた。
1947年の肺炎による死亡率(人口10万人あたり)は約155.2だったが、抗生物質の普及により1970年には34.8、2000年には88.0(高齢化の影響で一時上昇)、そして2020年には75.4となっている。
出産も命がけだった。
1950年の妊産婦死亡率(出生10万人あたり)は161.2で、約620人に1人の妊婦が出産時に亡くなっていた。
これが2022年には2.7まで低下し、約37,000人に1人となった。
約60分の1の水準だ。
外科手術の成功率も極めて低かった。
麻酔が確立される前の19世紀前半、手術は患者を縄で縛り付けて行われ、痛みによるショック死が頻発していた。
感染症予防の概念がなかったため、手術後の感染症による死亡率は30〜50%にも達していた。
これらのデータが示すのは、医学と薬学の発達以前、人類の生活がいかに過酷だったかという事実だ。
「薬石無効」という言葉が生まれた背景には、あまりにも多くの病気に対して医療が無力だったという歴史的現実がある。
医学史上の三大革命とデータで見るその影響
人類の医学史において、特に大きな転換点となった三つの発見がある。
ワクチンの開発、抗生物質の発見、そして麻酔法の確立だ。
これらの革命的進歩が、人類の寿命と生活の質をどれほど向上させたかを、具体的なデータで検証していこう。
革命その1:種痘の発明と天然痘の根絶
1796年5月14日、イギリスの開業医エドワード・ジェンナーは、使用人の息子ジェームズ・フィリップスという8歳の少年に、乳搾りをする女性サラ・ネルムズの腕にできた牛痘の膿を接種した。
6週間後、少年に天然痘を接種したが、少年は天然痘を発症しなかった。
これが人類初のワクチン接種だ。
ジェンナーの種痘は急速に普及した。
1800年までに、イギリス全土で少なくとも10万人が牛痘種痘を受けていた。
1800年の第3報論文でジェンナーは、6,000名以上が牛痘種痘を受け、その大部分に人痘種痘を行っても発病しなかったと報告している。
種痘の効果は驚異的だった。
天然痘による死亡率は、種痘普及前のイギリスでは人口1,000人あたり年間約3人だったが、種痘普及後の1800年代後半には約0.5人まで減少した。
約6分の1だ。
日本では1849年に佐賀藩で種痘が始まり、1858年に江戸幕府が種痘所(後の東京大学医学部の前身)を設立した。
明治政府は1876年に種痘規則を制定し、全国的な普及を図った。
1948年には種痘が法律で義務化され、1955年以降、日本国内での天然痘患者の発生はゼロになった。
世界規模では、1958年にWHOが世界天然痘根絶計画を開始。当時、世界33カ国に天然痘が常在し、年間約2,000万人が発症、約400万人が死亡していると推計されていた。
徹底した「サーベイランス・封じ込め作戦」により、1978年の患者報告を最後に地球上から天然痘は消滅した。
1980年5月、WHOは天然痘の世界根絶宣言を行った。
ジェンナーの種痘実験から184年後のことだ。天然痘は、人類が初めて根絶したウイルス感染症となった。
推計では、天然痘根絶により1980年以降の40年間で約1億2,000万人の命が救われたとされる。
革命その2:ペニシリンの発見と抗生物質時代の到来
1928年9月、イギリスの細菌学者アレクサンダー・フレミングは、ブドウ球菌を培養していた培養皿に偶然アオカビ(Penicillium notatum)が混入しているのを発見した。
そのカビの周りだけ細菌の発育が阻止されていることに気づき、カビの中に菌の成育を抑える成分があることを突き止めた。
これがペニシリンの発見だ。
しかし、フレミングは細菌学者であって化学者ではなかったため、ペニシリンを医薬品として製品化することができなかった。
12年後の1940年、オックスフォード大学のハワード・フローリーとエルンスト・ボリス・チェインが、ペニシリンの開発と大量生産に成功した。
第二次世界大戦が、ペニシリンの実用化を加速させた。
1944年のノルマンディー上陸作戦の際、連合軍が携帯したペニシリンの約90%をファイザー社が生産した。
ペニシリンは戦場での感染症による死亡率を劇的に減少させた。
戦前の戦傷における感染症死亡率は約30〜40%だったが、ペニシリンの導入により第二次世界大戦末期には約5〜10%にまで低下した。
約6分の1から8分の1だ。推計では、ペニシリンにより第二次世界大戦中に約10万人以上の兵士の命が救われたとされる。
日本では、1944年11月に陸軍が独自にペニシリンの開発に成功し「碧素」と命名した。
世界で3番目のペニシリン開発国となった。
しかし、戦時中の生産量は極めて限定的だった。
本格的な普及は戦後、1946年から占領軍の指導のもと製薬各社が生産を開始してからだ。
ペニシリンの普及による効果は絶大だった。
日本において、感染症による死亡率(人口10万人あたり)は、1947年の約180から、1960年には約40へと、わずか13年間で約4分の1に減少した。
乳児から高齢者まで全ての年齢層で感染症による死亡率が著しく減少し、平均寿命の上昇に大きく貢献した。
ペニシリンの成功は、他の多くの抗生物質の開発を促した。
1943年にストレプトマイシン(結核治療薬)、1947年にクロラムフェニコール、1948年にテトラサイクリン系抗生物質と、次々に新しい抗生物質が発見・開発された。これらにより、肺炎、結核、敗血症、髄膜炎など、かつて致命的だった多くの細菌感染症が治療可能になった。
革命その3:麻酔法の確立と外科医療の発展
1803年、日本の医師・華岡青洲が、独自に開発した全身麻酔薬「通仙散」を用いて、世界初の全身麻酔による乳がん摘出手術に成功した。
これは西洋で全身麻酔手術が行われる約40年前の快挙だった。
西洋では、1842年にアメリカのクロフォード・ロングがエーテル麻酔による手術を行い、1846年にウィリアム・モートンがエーテル麻酔の公開実演に成功した。
1847年にはジェームズ・ヤング・シンプソンがクロロホルム麻酔を導入した。
麻酔法の確立は、外科医療を革命的に変えた。
麻酔以前の手術では、速さが最重要視された。
ある外科医は脚の切断手術を2分以内で完了することで知られていた。
麻酔の導入により、医師は時間をかけて丁寧な手術ができるようになった。
さらに、1867年にジョセフ・リスターが消毒法を確立したことで、手術後の感染症による死亡率が劇的に低下した。
リスターの消毒法導入前の手術死亡率は約45〜50%だったが、導入後は約15%にまで低下した。
約3分の1だ。
20世紀に入ると、外科医療は飛躍的に発展した。
1954年に世界初の臓器移植(腎臓移植)が成功し、1967年には心臓移植が行われた。
1980年代には内視鏡手術が普及し、患者の身体的負担が大幅に軽減された。
2000年代にはロボット支援手術が実用化され、より精密な手術が可能になった。
これらの進歩により、かつては「薬石無効」とされた多くの疾患が治療可能になった。
胃潰瘍や十二指腸潰瘍は、1980年代までは手術が主な治療法だったが、H2受容体拮抗薬やプロトンポンプ阻害薬の登場により、現在ではほとんどが薬物療法で治癒する。
現代医療が直面する新たな課題とデータが示す未来
医学の進歩により、人類は多くの疾患を克服してきた。
しかし、平均寿命の延伸は鈍化し始めており、新たな課題に直面している。
イリノイ大学とカリフォルニア大学などの研究チームが2023年に発表した研究によれば、1990年から2019年までの長寿国8カ国(オーストラリア、フランス、イタリア、日本、韓国、スペイン、スウェーデン、スイス)および香港と米国の平均寿命の伸びが鈍化していることが判明した。
20世紀における驚異的な平均寿命の伸びは、主に死亡率の減少によるものだった。
しかし、研究チームの試算では、世界最長寿の日本人女性をモデルにした場合、平均寿命が100歳に達する際には約6〜7%の日本人女性が150歳に到達することになる。
現実的には、さらなる死亡率の低減と「老化の速度を遅らせる画期的な発見」がない限り、今世紀中に平均寿命が100歳に達することはないと予測されている。
実際、日本の平均寿命は2021年、2022年と連続して短縮した。
新型コロナウイルス感染症の影響と老衰による死亡率の変化が主な要因だ。
2024年の平均寿命は男性81.09歳(前年から横ばい)、女性87.13歳(前年から0.01歳短縮)となり、実質的に延伸が止まっている。
死因の構造も変化している。
2024年の死亡確率(ゼロ歳時)を見ると、男性の第1位は悪性新生物(がん)25.59%、第2位は心疾患13.70%、第3位は老衰8.39%となっている。
女性では第1位が老衰20.75%、第2位が悪性新生物19.06%、第3位が心疾患14.77%だ。
注目すべきは、老衰による死亡率の増加だ。
男女ともに老衰による死亡率が年々増加しており、女性では前年に続き死因第1位となっている。
がん・心疾患・脳血管疾患については死亡率が年々低下しており、医療水準の向上と生活習慣改善による予防の効果と見られる。
厚生労働省の試算によれば、2024年に悪性新生物、心疾患、脳血管疾患の3疾患すべてを克服できた場合、男性で約5.1年、女性で約4.4年、平均寿命が延びる計算だ。
しかし、これらの疾患を「完全に克服」することは現実的ではない。
平均寿命と健康寿命の差も重要な課題だ。
2019年のデータでは、健康寿命(健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間)は男性72.57歳、女性75.45歳だった。
平均寿命との差は、男性で約8〜9年、女性で約11〜12年ある。
この期間には医療費や介護費が多く発生する。
2000年に介護保険制度が導入されて以降、介護給付費は急増している。
2000年度の介護給付費は約3.6兆円だったが、2022年度には約11.5兆円と約3.2倍に増加した。
高齢化の進行により、2040年度には約25兆円に達すると予測されている。
しかし、医学の進歩は止まっていない。
2001年にはヒトゲノムの解読が完了し、個別化医療への道が開かれた。
抗体医薬、遺伝子治療、再生医療など、新しい治療法が次々と開発されている。
がん治療では、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬により、かつては治療困難だった進行がんでも長期生存が可能になりつつある。
AI(人工知能)の医療への応用も進んでいる。
画像診断支援、創薬支援、個別化治療の最適化など、AIが医療の質と効率を向上させる可能性が期待されている。
まとめ
薬石無効という言葉が生まれた9世紀から現在まで、人類は医学と薬学において驚異的な進歩を遂げた。
データが示すその軌跡は、まさに奇跡と呼ぶにふさわしい。
約5万年前、ネアンデルタール人が薬用植物を使用していた可能性のある時代から、紀元前3000年のメソポタミアで最初の薬学書が粘土板に刻まれ、紀元前400年にヒポクラテスが科学的医学の基礎を築いた。
1796年にジェンナーが種痘を発明し、1928年にフレミングがペニシリンを発見し、人類は感染症との戦いに勝利の道筋をつけた。
その結果、日本の平均寿命は明治期の約43歳から現在の約84歳へと、約40年延びた。
乳児死亡率は約40分の1に、感染症死亡率は約4分の1に、妊産婦死亡率は約60分の1に減少した。
天然痘は地球上から根絶され、結核やポリオなど多くの感染症が制御可能になった。
かつて「薬石無効」とされた病気の多くが、今や「薬石有効」となった。
胃潰瘍は手術なしで治癒し、肺炎は抗生物質で治療でき、がんですら早期発見により高い確率で治癒可能だ。
外科手術は麻酔と消毒法の確立により安全性が飛躍的に向上し、臓器移植や再生医療により、かつては不可能だった治療が現実になっている。
しかし、データはまた新たな課題も示している。
平均寿命の延伸は鈍化し、健康寿命との差は依然として大きい。
高齢化により医療費・介護費は増大し続けている。
がん、心疾患、認知症など、完全な克服にはまだ遠い疾患も残されている。
それでも、医学の進歩は続いている。
ゲノム医療、再生医療、AI医療、個別化医療など、新しい技術が次々と開発されている。
人類は「薬石無効」を「薬石有効」に変えてきた歴史を持つ。
この歴史が示すのは、科学的探求と技術革新により、人類は困難を克服し続けてきたという事実だ。
stak, Inc.が開発するIoTシステムも、この医療の進化に貢献する可能性を秘めている。
健康データのモニタリングと分析により、疾患の早期発見と予防が可能になる。
テクノロジーと医学の融合が、次の医療革命を生み出すかもしれない。
唐の宣宗が「薬石効なく」と嘆いた時代から1200年。
人類は薬と医療を通じて、驚異的な進歩を遂げてきた。
そしてこの進歩は、今もなお続いている。
データが示すこの軌跡は、人類の叡智と不屈の精神の証だ。
未来の医療がどこまで進化するかは未知数だが、過去のデータが教えるのは、人類は常に前進し続けるということだ。
【X(旧Twitter)のフォローをお願いします】