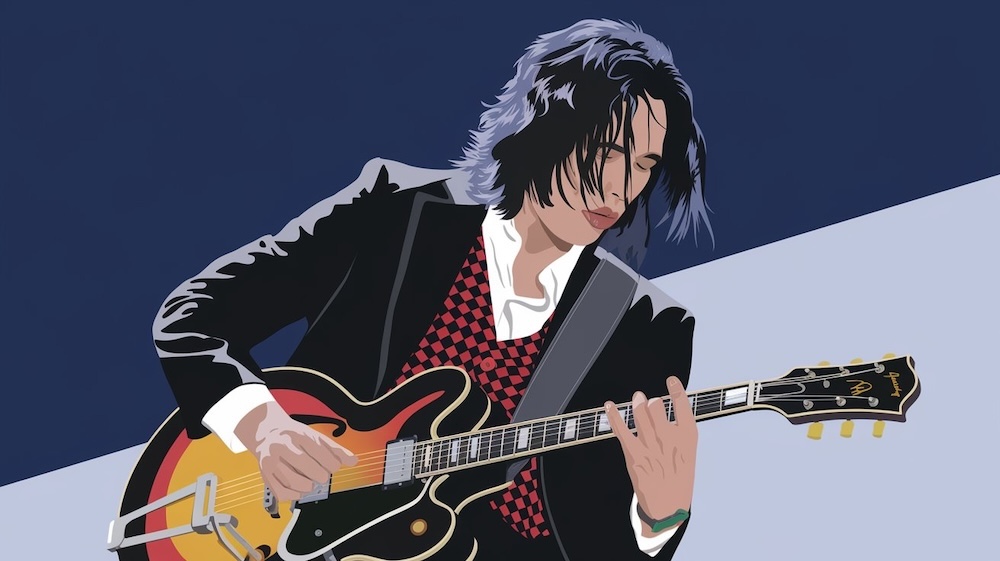悲歌慷慨(ひかこうがい)
→ 悲壮に歌い世を憤り嘆くこと。
悲歌慷慨という言葉は古代中国の文化圏で生まれ、時代を経て日本にも伝わった概念だ。
悲しみや嘆きを胸に抱えながらも、それを慷慨の情、すなわち熱い憤りや義憤をもって歌うという風潮が背景にある。
中国の古典『詩経』には、民衆の苦しみや政治への批判を歌い上げる詩が多く存在し、それが後世の悲歌慷慨の源流となったと言われている。
日本でも平安時代以降、乱世に対する嘆きや無常観、あるいは政治への不満などを詠った詩歌が盛んになり、江戸時代になると知識人や文人たちが憤懣を筆や声に乗せて表現した。
この悲歌慷慨の精神は、本来なら世の中の矛盾や不条理を多くの人々に伝え、変化を呼び起こす力になり得るはずだ。
しかしながら、現代ではSNSやメディアの発達に伴い、やたらと大きなテーマだけを批判し、あたかもそれが自らの存在価値だと信じ込んでしまう人が散見される。
それ自体は自由だが、実際のところ、そうした声が社会にどれほど影響を与えているかを冷静に見極める必要がある。
誰も憤りと嘆きを聞いていない現実
SNSの普及によって、あらゆる人が瞬時に意見や感想を世界へ向けて発信できる時代になった。
しかし、大した実績や影響力を持たない人間が「世界経済がどうの」「アメリカの大統領がどうの」「戦争がどうの」と悲歌慷慨を語っても、ほとんどのケースで誰にも届かない。
フォロワー数が極端に少ないアカウントの激烈な政治批判がバズる確率はごくわずかだし、実際にそれが政策や社会問題を動かす可能性はさらに低い。
Statistaのレポート(2021年)によると、SNS全体の投稿のうち、一つの投稿が1,000件以上のエンゲージメント(いいね・コメント・シェアなど)を獲得する割合はわずか1%以下とのデータがある。
つまり、多くの人は声なき声として埋もれ、自分だけが世界に向けて吠えているような気になっているにすぎない。
悲歌慷慨は誰もが簡単にできるが、その声を本当に世に届けたいのであれば、聞いてもらえるだけの実力や信頼、あるいは魅力を身につけることが先決だということだ。
さらに厳しい現実として、声だけは大きい人の多くは、実際に大勢の前や公の場に呼ばれると尻込みしたり逃げたりする傾向も指摘されている。
SNSやネットの匿名性に守られているからこそ強気になれるのであって、生身の場では責任を負いたくないという裏返しでもある。
そうした「何者でもない人」の声に真面目に耳を傾けるほど、世の中は甘くはない。
まずは自分が影響力を持つことへの道
大きなテーマに物申すのは自由だが、誰も耳を貸さない現実を受け止めたうえで、まずは自分自身が影響力を持つ努力を積み重ねるべきなのである。
影響力といっても有名人になる必要はなく、身近なコミュニティや仕事仲間、取引先など、まずは半径5メートルの範囲で信頼を獲得することから始めるのが現実的だろう。
マーケティングの観点では、マイクロインフルエンサー(フォロワー数1万人未満の個人)が企業のプロモーションにおいて高いエンゲージメント率を持つというデータがある。
Influencer Marketing Hubが2022年に発表した調査では、フォロワー数が少ないほどコメントやリアクションの割合が高く、結果的に広告効果が上がる傾向が見られた。
これは大きな声よりも、密度の濃いコミュニケーションが支持を集めるというエビデンスにほかならない。
つまり、いきなり世界を批判して影響力を得ようとするのではなく、今いる場所で周囲を巻き込む力を持つことが重要だ。
stak, Inc.で提供している機能拡張型IoTデバイスの開発も、当初は限られたリソースと限られた顧客との小さなコミュニティから始まった。
その中で実際に役立つ機能を生み出し、ユーザーとの信頼を積み重ねることで徐々に世の中への発信力を拡大してきた経緯がある。
大きなことを言う前に、小さな成功体験を積み上げることが何よりの近道だという経験はいくつもしてきた。
大きなテーマの批判より目の前の課題解決
「日本経済が停滞している」「某大国の大統領が気に入らない」「資源価格の高騰が世界を混乱に陥れている」など、膨大なスケールの話題は魅力的だ。
誰かを批判し、自分はわかっているというポジションを取ると、気分が良くなるのも確かである。
しかし、そうした大きなテーマを論じたところで、自分自身がその解決に直接関われる段階にないならば、ほとんど無意味なのだ。
実際に世の中を変えてきた人々は、最初から大きなテーマに飛びつくのではなく、手の届く範囲の課題を解決することからスタートしている。
かつてGoogleがガレージから始まったように、ほんの小さな検索アルゴリズムの工夫が、情報検索の世界を根底から変えた事例が代表的だろう。
AppleやAmazonも同様に、最初は極めてニッチな顧客に向けて、パーソナルな問題を解決する製品・サービスを提供することから歴史を刻んだ。
政治を批判したり、世界の動きを憂えたりするのは簡単だが、それで日々の仕事や人生の課題が前進するわけではない。
まずは目の前にある問題を一つひとつ解決し、その成功体験を蓄積していくことこそが、自分のブランド力や信用力を高める最短ルートだ。
悲歌慷慨で叫ぶよりも、解決策を提示できる存在を目指すことが大切である。
小さな積み重ねが大きな変化を生むエビデンス
世を変えるほどの影響力は、突然得られるものではない。地道な積み重ねが大きな岩をも動かす。
これは数多くの事例が示している。
とくにデジタルマーケティングの世界では、毎日ブログやSNSなどで有益なコンテンツを投稿し続けた結果、一年後には驚くほどのアクセス数やフォロワー数に繋がったというケースが多々ある。
HubSpotの調査(2020年)によれば、企業ブログを月に16回以上更新する組織は、月に0〜4回更新する組織と比較して、約3.5倍のリードを獲得するというデータが公表されている。
こうしたデータは、継続的な情報発信や地道なコミュニケーションが、いかに大きな成果を生むかの証明だと言える。
悲歌慷慨をこじらせて嘆き続けるより、まずは自分の専門分野や関心領域で役立つ情報をアウトプットし、それを見た人に一歩でも行動のきっかけを与えればいい。
その積み重ねが「この人は信用できる」「この人は有益な情報源だ」という評価につながり、やがては大きなムーブメントを起こす火種になる。
さらに一度築いた信頼は、周囲を巻き込みながら加速度的に拡散する。
IoT、AI、クリエイティブ、マーケティングといった最先端分野であっても、基礎的な実績や小規模での成功事例が積み重なることで、大企業や行政を動かすようなレベルのインパクトにつながる。
stak, Inc.もまさに、小さな課題解決を積み上げた先に多くの企業との連携が生まれ、新しいサービスのアイデアが現実のものになっている。
まとめ
stak, Inc.のCEOとして常に感じるのは、「悲歌慷慨をしているヒマがあるなら、一歩でも前に進むべきだ」ということだ。
大きな声で社会を批判するより、自分が手を動かして生み出すサービスや製品の質を上げること、そしてユーザーを増やし、ファンを育てることが結果的には社会を動かす力になる。
stakは機能拡張型IoTデバイスを通じて、「こんな機能があったら助かる」「こういうアイデアは世の中の役に立つはず」というユーザーの声を形にしてきた。
最初は限られた範囲のアイデアだったとしても、それを実証し、改良を続け、新たな機能を実装し、さらにPRやブランディングを強化することで、世の中に少しずつ存在感を示してきた。
こうした小さな成功の積み重ねが、やがては大きなイノベーションへとつながると確信している。
要は、影響力のない段階でいくら悲歌慷慨を叫んでも、時代は動かないし誰も振り向かない。
だが、コツコツと自分の専門を極めて価値を提供し続ける人間こそが、最終的には大きなうねりを起こす力を手に入れる。
悲歌慷慨を超越する手段は常にシンプルで、まずは目の前の課題を解決すること。
その積み重ねが未来を変える最大の原動力となる。
自分自身の存在を世界へと伝えたいなら、世の中の不条理への嘆きよりも、自分が動いて何かを創り出す方が圧倒的に価値がある。
小さなコミュニティから始めた取り組みが、巡り巡って想像以上に広がることを、stak, Inc.としても経験してきた。
だからこそ、悲歌慷慨を悲壮に歌うのではなく、動き出すことこそが社会を変革する唯一の道だと言い切る。
この考え方を共有してくれる仲間やファンが増えれば増えるほど、stak, Inc.はもちろん、個人としての自分もより大きなステージで戦うことになる。
その時になって初めて、世界へのメッセージが重みを持ちはじめる。
悲歌慷慨を越え、実力で未来を変える。そこに本当の成長と影響力が宿ると確信している。
【X(旧Twitter)のフォローをお願いします】