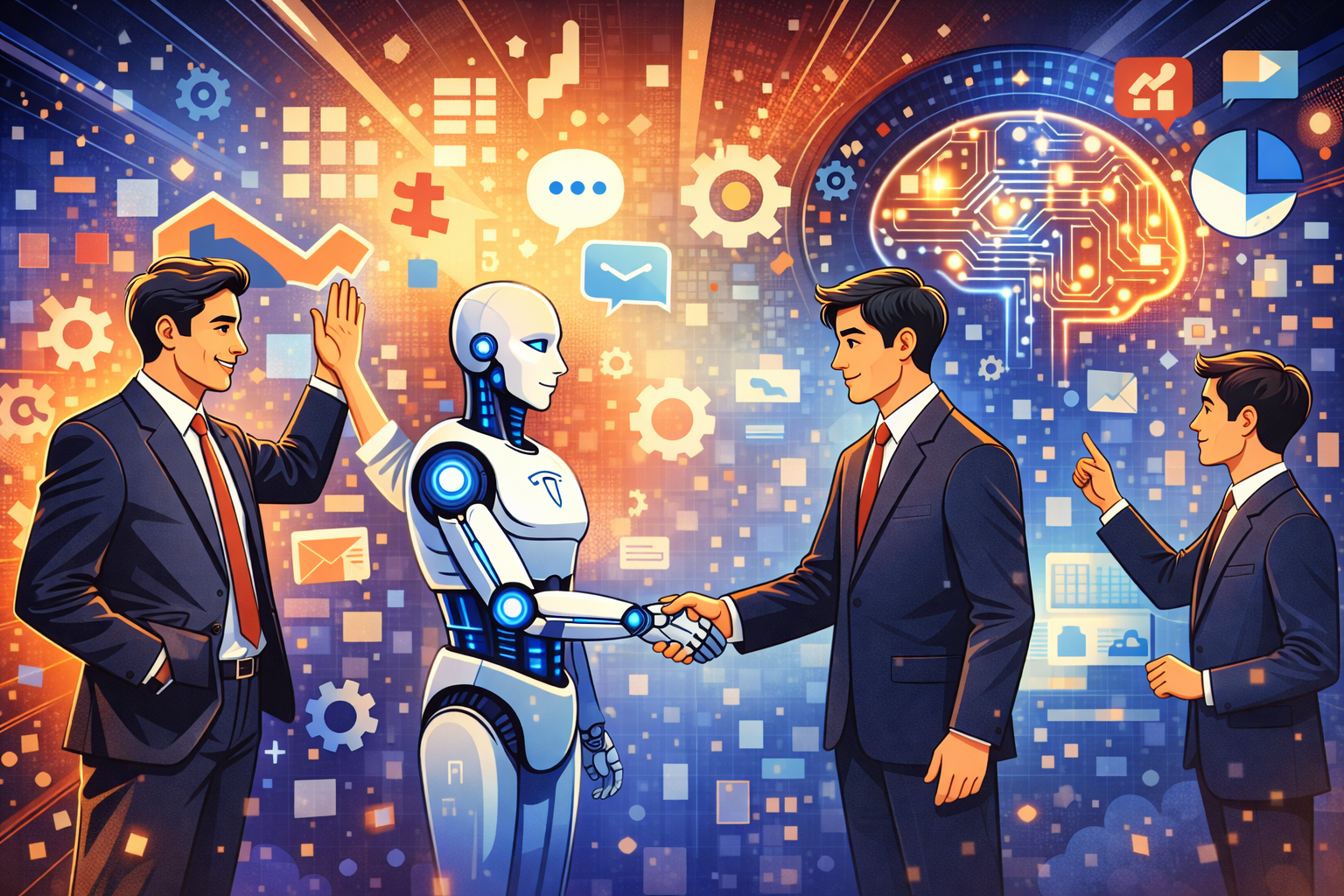枯木寒巌(こぼくかんがん)
→ 世俗を離れた無心の境地や冷たく素っ気ない様子。
都心を離れて暮らそうとしている人たちが増えているという情報を耳にすることがあるが、本当なのだろうか。
そういった記事を目にすることもあるが、どこか誘導しているような気がしなくもない。
というのも、若者が世俗を離れようとしているとか、冷めている感じの演出をしているようなイメージが少なからずあるということだ。
私自身が10代や20代と接する機会が増えて思うのは、表現の仕方に変化が起きていて、根本にあるエネルギーのようなものは不変だと感じている。
もちろん、人それぞれなのでひとまとめにすることはできないが、こんな記事に目を留めたので紹介していこう。
とある村に移住する若者たち
まずはこちらの記事を読む時間のある人は見てもらいたい。
(出典:ダイヤモンド・オンライン)
東京との県境にある山梨県に人口わずか530人の小さな村がある。
その名を丹波山(たばやま)村といい、鉄道も通らず、コンビニもないという。
現代の生活になれていると、不便だと感じることは間違いない丹波山村だが、ここ数年、若者の移住や起業が相次いでいるそうだ。
なぜ、若者たちはこの丹波山村で暮らすことを選んだのかについて書かれているので追いかけていこう。
まず、丹波山(たばやま)村のスペックだが、東京の新宿から電車を乗り継いで1時間半程度で、村を東西に貫く丹波川は多摩川の源流で、村の面積の97%を森林が占める。
高校がないため、若者たちは中学卒業と同時に村を離れ、多くは県外で就職したまま戻ってこないので、日本全国のどこの村にでもある人口減少と高齢化問題がある。
実際、1960年に2,200人余りいた人口は、2022年9月時点で534人にまで減った。
そこに大学を出て間もない都会の若者たちが、移り住んでいるという。
きっかけは大学の授業
とある移住者の例が挙がっているが、私の母校である中央大学の出身者であったことに少々親近感を覚えた。
それは置いておいて、丹波山村に移住するきっかけになったのが、ソーシャル・アントレプレナーシップ・プログラムという科目を履修したことだとある。
その授業は、丹波山村を含め、人口減少が進む3つの自治体から1つを選び、地域の課題を解決するサービスや商品を開発するというものだそうだ。
移住者の彼は、正直なところエリアにこだわりはなく、3つのうち丹波山だけ村の名前が3文字でここでいいやくらいの気持ちだったという。
履修1年目は都内の自宅から村に通い、農業の収穫やイベントを手伝った。
ところが、2年目の春は国内で新型コロナウイルスの感染が広がり始め、往来が難しくなった。
せっかく履修しているからには、もう少し村のことを知りたいと考えた彼は、大学がオンライン授業に移行していたことも手伝い、村に家を借りて、週の半分以上を過ごすようになったという。
こうしているうちに、大学4年制のときに起業の決意が固まったそうだ。
村内にある空き家を調査するプロジェクトに関わり、空き家を生まない仕組みを作り、全国展開できればビジネスとしても成り立つのではないかと考えるようになったのだという。
また、村の人たちと関わるうちに恩返しせずには帰れないという気持ちも大きかった。
そして、現在は村からの受託業務という形で、村内にある空き家の持ち主や活用の意向について調査を続けているそうだ。
地域おこし協力隊の存在
地域おこし協力隊という制度を知っているだろか。
地域おこし協力隊は、2009年度から総務省がスタートさせた制度だ。
1〜3年以下という決まった期間、都市部にいる人材が地域おこし協力隊員として地方に移住し、地方自治体の委託を受け地域の問題解決や発展のための活動を行うという制度をいう。
名産品を活かした商品開発、旅行の企画運営、住民の交流の場づくりといった具合いに、募集する人材や従事する仕事内容や報酬は地方自治体によって様々だ。
この地域おこし協力隊の存在も地方創生の一翼を担っていて、1人の若い女性が丹波山村へ移住したきっかけもまさにそこだったという。
新潟県長岡市出身の彼女は、大学卒業後に丹波山村の存在を地域おこし協力隊の求人を通じて知り着任したそうだ。
育った場所は過疎化が進み、小学校の同級生は全校あわせて30人ほど。
面接で初めて村に訪れたとき、一面を山に囲まれた風景に圧倒されて、ここで暮らしてみたいと思ったという。
東京から意外とアクセスがいいのも決め手の1つだった。
そして、現在は丹波山村の観光推進機構に所属し、飲食店でテイクアウト商品の開発や販売に携わっている。
彼女は大学時代、コーヒー同好会に所属していたことから、コーヒーを使った地域おこし活動にも関心があるということだ。
地域おこし協力隊の成果
丹波山村が地域おこし協力隊の募集を始めたのは2014年。
初年度の採用者は4人だったが、受け入れを始めると村内の事業者から、うちにも来てほしいと声が相次ぎ、2022年は18人に増えて、採用総数は延べ35人になっている。
そして、地域おこし協力隊の受け入れが始まってから8年間で、村の人口は110人ほど減りましたが、20代から40代が村全体の人口に占める割合は2.2%ほど増えたという。
この新たな移住者の呼び込みができているということがポイントで、村役場に就職した若者もいる。
村を訪れてから移住に踏み切るのではなく、移住を考えて初めて村を訪れたというパターンになっていることが、地域おこし協力隊の成果だといえるだろう。
ひとくくりに若者ということは難しいが、移住してくれる人が増えるというのは村にとってプラスでしかない。
もともと、田舎暮らしに興味があっても、情報を発信している自治体は意外と少ない。
あるいは、探している側も移住の条件が少々悪くてもいいと考えている人は案外多い。
その条件が悪いというところも、必ずしも経済的な部分だけではなく、飲食店やコンビニがないといった物理的なところも含めてだ。
このギャップが、地域おこし協力隊のおかげで少しずつ埋まっている現状があることを知っておくといいだろう。
そこには、インターネットの普及が影響していることは絶対だ。
どんな自治体でどういった採用募集があるのか、誰でも簡単にアクセスできるようになっているサービスが増えているし、SNSで情報を収集することも可能になった。
また、飲食店やコンビニがなくても、Amazonのようなサービスがあるので、都会での生活とそこまで大きく変化なく過ごすこともできる。
なによりも、そもそも都会を離れようとしている人なのだから、そのあたりのギャップが著しくなければ来てもらえるチャンスが多くあることに気が付かされているのである。
それから、私自身はそうも思わないが、人の温かさを感じることにプライオリティを置く人も多いということも挙げておこう。
これもインターネットの普及の悪い面としてよく挙がる例なので、まあ言わんとしていることは理解できるし、いずれにせよ人を呼び込むきっかけになっているのは認めざるを得ない。
まとめ
地方創生を目論んでいる自治体の人たちは、この事例はしっかりと把握しておくべきだろう。
ポイントをまとめると、まずは情報をしっかり発信していることが大前提にある。
それから、都会から近いことが成功事例としては重要だというのが、現行の流れだ。
今回紹介した記事の内容も首都圏の近くにあることがポイントになっていることは理解できるだろう。
ただし、この部分についてはもっと上手にやれば都会からある程度離れていたとしても、人を呼び込むことは可能だと思っている。
そのためには強いコンテンツが重要になることは間違いないが、それも込みで呼び込むことをしなければ、そんなに人の心を動かすことは簡単ではないことも同時に知っておくべきだろう。
【Twitterのフォローをお願いします】