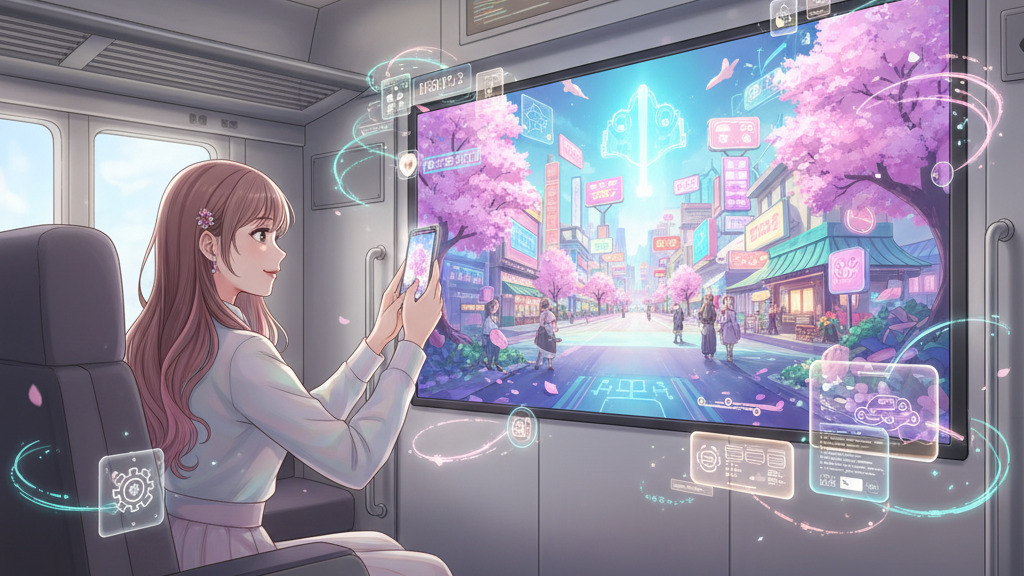こんにちは、さこです!
先日、新幹線に乗っていたときに、思わず見入った広告がありました。
JR西日本コミュニケーションズが掲出していた「広告出稿案内」、いわば広告主向けの営業用の広告です。

江戸の街並みをイメージしたイラストです。
ぱっと見は浮世絵調で、時代を感じさせる雰囲気がありますが、ビジュアルそのものが特別目立っていたわけではありません。
私の目を引いたのは、そのイラストの右下に小さく添えられていた注意書きでした。
「この画像は生成AIで作成したものです。」
SNSやニュースではAIアートを目にする機会が増えていますが、公共交通という、誰もが日常的に利用する空間で「生成AI」という文字をはっきりと見たのは印象的な体験でした。
この注意書きは、単なる制作方法の説明にとどまらず、広告における「透明性」や「信頼のあり方」を考えさせてくれるものでした。
この記事では、その広告をきっかけに「公共空間におけるAI活用の今とこれから」について整理してみたいと思います。
公共空間に現れたAI生成広告の意味
これまでAIで作られた画像といえば、SNSの投稿やブログのアイキャッチ、オンライン上のバナー広告など、いわゆる「デジタル空間」で使われるものが中心でした。
ネットをよく使う人なら頻繁に目にする一方で、普段あまりネットに触れない人にとってはまだ馴染みが薄い領域だったかもしれません。
ところが今回のように、新幹線の車内広告という公共空間にAI生成のビジュアルが使われ、しかも「AIで作りました」と明記されるケースはこれまで多くはありません。
新幹線を利用する人は、通勤するビジネスパーソンから観光客、さらには修学旅行の学生まで、本当に幅広い層にわたります。
特定のターゲットに絞られるネット広告とは違い、不特定多数が同じ広告を見るのが車内広告の特徴です。
そんな場所でAI活用を開示することには、いくつかの意味があると考えられます。
1. AI活用の可視化
まずひとつは、社会全体への「AI活用の可視化」です。
AIはすでに多くの業界や私たちの生活に浸透してきていますが、まだ「自分の身近なもの」として実感していない人も少なくありません。
公共広告で「生成AI」と明記されることで、AIが特別な技術ではなく、身近なツールになりつつあることを自然に意識させられます。
2. 教育的な役割
次に、教育的な役割です。
広告を見た人が「えっ、こんな絵もAIで作れるの?」と気づくこと自体が学びのきっかけになります。
公共交通広告は、単なる宣伝を超えて、社会全体にAIの存在を少しずつ浸透させる役割も果たしているのです。
3. 安心感の提供
そして最後に、安心感の提供という側面もあります。
もし何も書かれていなかったら、一部の人は「これは本物?それともAI?」と疑念を持ったかもしれません。
あえて表記をすることで、「隠していないんだな」と感じられ、安心して受け止めてもらえる可能性が高まります。
なぜ「生成AIで作成した」と書くのか
では、そもそもなぜ「生成AIで作成した」とわざわざ明記するのでしょうか。
法律やルールで義務づけられているわけではありません。つまり企業側が自主的に判断しているのです。
理由は大きく三つ考えられます。
ひとつ目は、誤解を防ぐためです。
生成AIは非常にリアルで本物らしい表現ができるため、人によっては写真や実際の絵と区別がつかないこともあります。
広告は多くの人に影響を与えるものだからこそ、誤解を避けるために明示しておくのは企業としての責任とも言えるでしょう。
二つ目は、消費者のリテラシーへの対応です。
最近では一般の人も「これってAIで作ったのかな?」と気づくケースが増えています。
そんな時代に隠してしまうと「なぜ言わないんだろう」と逆に不信感を持たれるリスクがあります。むしろ最初から正直に開示する方が、信頼を積み重ねやすいのです。
三つ目は、ブランド価値の向上です。
透明性を積極的に示すことは、「誠実さ」「先進性」といったイメージを育てることにつながります。
特にJRのように公共交通を担う企業にとって、利用者の信頼は何よりも大切。広告に込められた姿勢は、ブランド全体の評価に直結すると言えるでしょう。
広告と透明性の進化
広告に注意書きがつくのは昔からの習わしです。
金融商品の広告にリスク説明が必要だったり、食品の広告で効能を強調しすぎないよう制限があったりと、ルールや配慮はさまざまに存在します。
その流れの中で「生成AIで作成した」という表記は、まさに新しい透明性の形です。
重要なのはこれは単なる規制対応ではなく、企業が自主的に選び取った判断だという点です。
消費者が「AIで作ったんだ」と理解したうえで広告を受け取れば、そこには誠実さが感じられます。
逆に、もし隠していることがわかれば、企業への信頼は一瞬で崩れてしまうかもしれません。
AI時代の広告では、「どうAIを活用するか」と同じくらい「それをどう伝えるか」がブランド戦略の一部になっているのです。
公共交通広告が持つインパクト
今回の事例が「新幹線の車内広告」だったことにも意味があります。
SNSやネット広告はターゲットを絞れる分、見てもらえる層は限定されます。
しかし新幹線は、日本中の多様な人が使う場です。ビジネスパーソンから観光客まで幅広い層が必ず目にする空間だからこそ、その影響力は大きいのです。
「生成AI」という小さな文字は、単なる技術紹介ではなく、AIが公共の場で正面から受け入れられ始めているサインだとも言えるでしょう。
広告におけるAIと透明性の未来
これから先、広告業界ではさまざまな変化が進んでいくはずです。
まず、AI利用の表記は今後どんどん一般化していくでしょう。
今は珍しい存在ですが、数年後には「AI生成」と書かれていることがごく当たり前になるかもしれません。
同時に、どこまで使ったら表記が必要なのかというルールづくりも欠かせません。
完全にAIで作った場合はもちろん、部分的に補正や構図案出しに活用した場合も対象にするのか、その線引きは業界全体の課題になります。
また、消費者の感じ方も変わっていきます。
今はまだ「AI生成」と聞いて不安に思う人もいますが、繰り返し開示されるうちに「AIは普通の道具なんだ」と認識され、違和感は薄れていくでしょう。
そして最後に、透明性をどう打ち出すかは、企業の差別化のポイントにもなります。
積極的に表記する企業は「誠実で信頼できる」と評価される一方で、開示に消極的な企業は批判を浴びるリスクを抱えることになるかもしれません。
まとめ
新幹線で出会った「この画像は生成AIで作成したものです」という小さな注意書き。
これは単なる制作過程の説明ではなく、広告がこれからどのように変わっていくのかを考えさせられる大切なサインでした。
公共空間でAIの活用をオープンにすることは、見る人に安心を与えるだけでなく、企業にとって信頼を築くチャンスにもなります。
これからの広告は「何を伝えるか」に加えて「どう作られたのか」を伝えることが、より一層重要になっていくのではないでしょうか。