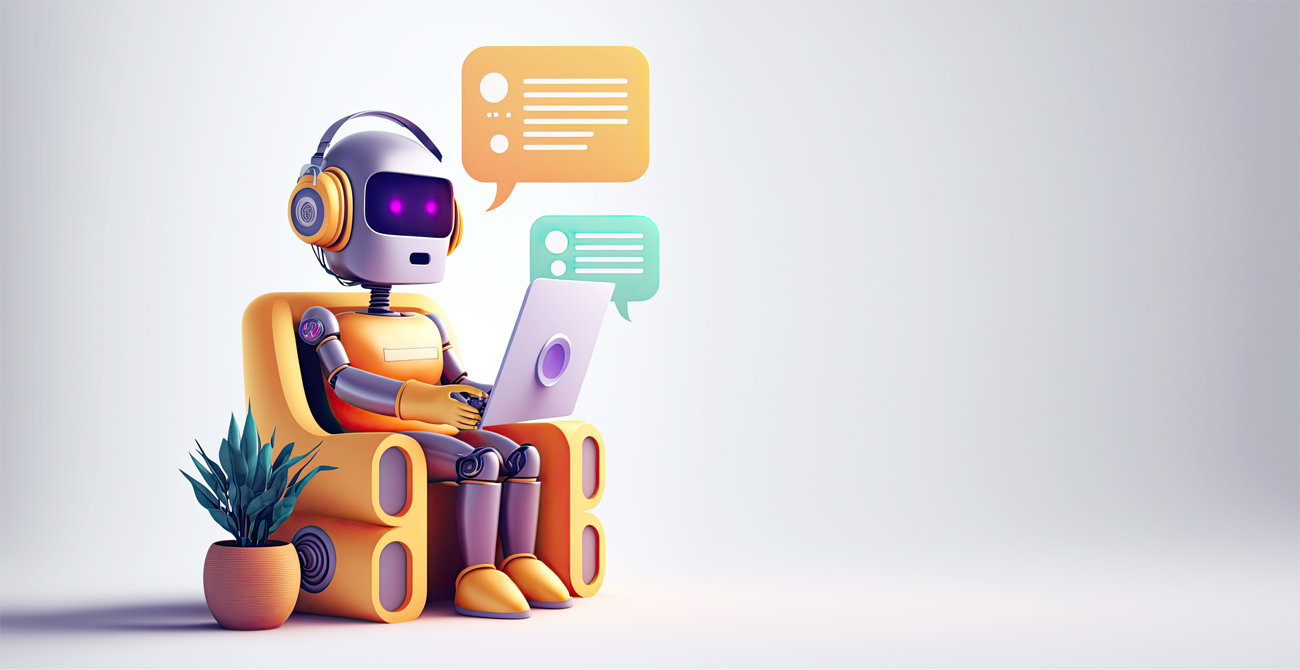こんにちは、さこです!
ここ数年で、AIチャットツールは一気に私たちの身近な存在になりました。
ChatGPTに代表されるようなAIは、調べものや文章の下書き、アイデア出し、ちょっとした相談ごとなど、あらゆるシーンで頼れる”相棒”のような存在になりつつあります。
実際、私自身もAIチャットボットはもう仕事に欠かせない存在です。
もし突然使えなくなったら、業務の進行にも大きな影響が出てしまうくらい、毎日のように活用しています。
プライベートでも「とりあえず聞いてみよう」と頼りにする場面は増えました。
ChatGPTやGemini、Claudeといったツールは、話しかけるだけで瞬時に返事をくれて、サクッと要点を整理してくれる便利さがあります。
使えば使うほど、「AIとの会話ってこんなに自然なんだ」と驚く人も多いでしょう。
でもその一方で、「話した内容が、思いがけず外に漏れてしまう可能性がある」というリスクも潜んでいることを、どれくらい意識していますか?
この記事では、私たちがAIと付き合ううえで気をつけたいプライバシーのこと、そして大切なアイデアや情報を守るためのポイントを、わかりやすく解説していきます。
AIは「ちょっとした会話」も忘れない
AIを何度か使ってみると、「あれ、このAI、前に話したことを覚えてる…?」と感じた経験はありませんか?
たとえば、「旅行が好き」と何気なく話したら、次の会話で「おすすめの旅先はここです」と提案してくれたり、「週末は混むので平日の方がいいですよ」なんて気の利いたアドバイスをくれたり。
こうした自然なやり取りの裏側には、AIがあなたとの過去の会話を記憶し、学習しているという仕組みがあります。
そして、その「ちょっとした発言」も、AIにとっては学習の材料。
あなたが忘れていても、AIはしっかり覚えているかもしれません。
さらに注意したいのは、あなたの話した情報が別の誰かとの会話に反映されてしまう可能性もあるということ。
たとえ個人が特定される形でなくても、「こんな相談をされたことがある」といった形でAIの返答に組み込まれる可能性もあるのです。
話した瞬間、それを手放したことになる
スタンフォード大学の研究員、ジェニファー・キング氏はこう述べています。
「チャットボットに何かを入力するということは、それを手放すことになる」
これはつまり、「もう自分だけの情報ではなくなる可能性がある」という意味です。
実際に2023年には、ChatGPTに関する不具合が発生し、他人のチャット内容が一部のユーザーに見えてしまうというトラブルがありました。
また、多くのAIサービスの利用規約には「ユーザーの会話内容をサービス改善のために使う場合があります」と明記されています。
つまり、あなたの入力が将来的に別のユーザーの回答に生かされることもある、ということです。
AIとの会話はどこか安心して話せる空気感がありますが、その裏にはデータの取り扱いがしっかり存在していることを忘れてはいけません。
発明アイデアをうっかり話すと、特許が取れなくなる!?
ここからは少し専門的な話になりますが、技術や企画開発に関わる方にはぜひ知っておいていただきたい重要な内容です。
最近増えているのが、未出願の発明や新規アイデアをAIに相談してしまうというケース。
これは特許の世界では非常にリスクが高い行為で、実際に弁理士の方々も注意を呼びかけています。
「発明のアイデアをAIに入力した時点で、“すでに公開された情報”とみなされて、特許が認められなくなる恐れがあります」
というのも、日本の特許法では「世の中にまだ知られていない新しい発明」であることが出願の条件です。
多くの生成AIはクラウド上で動いており、入力した内容はインターネットを通じてサーバーに送られます。
その送信プロセス自体が、「技術的に第三者が見ようと思えば見られる状態」と判断されてしまう可能性があるのです。
さらに、ChatGPTなどの生成AIは「入力された情報を学習に利用する場合がある」と利用規約に明記していることがほとんどです。
つまり、あなたが入力した発明のアイデアが、知らない誰かへの回答に断片的に使われるリスクもゼロではないということです。
特許アイデアを扱うときに気をつけたいこと
-
特許出願前のアイデアや技術的な内容は、どんなに軽い話でもAIに話さないこと
-
AIを使う場合は、社内環境で完結するローカルAI(外部と通信しないもの)を使う
-
利用するAIサービスの利用規約・プライバシーポリシーを事前に確認し、「学習に使われない設定」ができるかチェックする
-
社内でAIの使い方ガイドラインを整備し、機密情報の取り扱いに関する共通ルールを持つ
AIに話してはいけない「5つの情報」
AIチャットとの会話では、つい「これも相談しちゃおう」と気軽に話しがち。
でも、以下の5つの情報だけは絶対に入力しないようにしましょう。
1)個人情報
- 名前、住所、電話番号、生年月日、マイナンバー、パスポート番号など
2)健康・医療に関する情報
- 検査結果、診断名、服薬履歴など。差別や偏見のリスクがある情報です。
3)金融情報
- 銀行口座番号、クレジットカード番号、投資先の詳細など
4)企業の機密情報
- 公開前プロジェクト、顧客リスト、戦略資料、ソースコードなど
5)ログイン情報
- ID、パスワード、「秘密の質問」など
一度入力してしまえば、その情報はAIシステムの中に残る可能性があり、悪意のある第三者に使われてしまうリスクも非常に高くなります。
安心して使うための対策
AIを安全に、かつ便利に活用していくために、次のような対策もぜひ取り入れてみてください。
「一時チャット」や「履歴の削除」を活用する
ChatGPTの「Temporary Chat」や、Claudeのようにチャットを自動削除してくれる機能を活用すれば、会話内容が保存・学習に使われるのを防げます。
匿名化ツールを使う
Duck.aiなどのツールを使えば、入力内容を匿名化してAIに送ることができます。
ただし、機能が限定されている場合もあるので、使い道に応じて選びましょう。
パスワードや認証の強化をする
AIにパスワードを教えるのではなく、信頼できるパスワード管理ツールを活用し、多要素認証でセキュリティを高めましょう。
「使わない」よりも「どう使うか」が大切
「なんだか怖いから、もうAIは使わない方がいいかも…」と思った方もいるかもしれません。
でも、大事なのは「使わないこと」ではなく、「どう使えば安心か」を考えることです。
AIはこれからますます生活の中に浸透していくツールです。だからこそ、正しい知識を持って、うまく使いこなす力が求められています。
最後に:安心してAIを使うために覚えておきたい3つのこと
-
個人情報やアイデアは入力しない
-
履歴やプライバシー設定をこまめにチェックする
-
「話す責任」を自覚し、情報管理の意識を持つ
ほんの少しの注意と工夫で、AIはこれからの時代を支えてくれる強力な味方になります。
ぜひこの記事の内容を思い出しながら、これからも安心してAIと付き合っていきましょう!