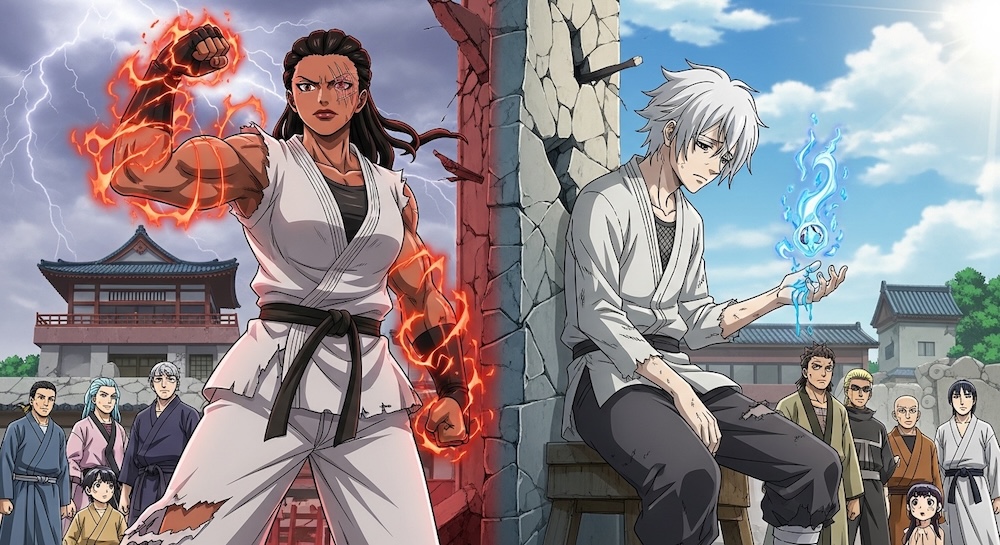毛骨悚然(もうこつしょうぜん)
→ 毛髪や骨の中まで恐れを感じる意から、ひどく恐れるさまを言う。
毛骨悚然という四字熟語は、中国の古典『史記』にその起源を持つ。
「毛」は体毛、「骨」は骨、「悚」は恐れおののく、「然」はその様子を示す。
つまり、体毛が逆立ち、骨の髄まで恐怖が浸透する様子を表現した言葉だ。
この表現が初めて文献に登場したのは紀元前1世紀頃。
司馬遷が編纂した『史記』の中で、恐怖による生理的反応を描写する際に用いられた。
人間が極度の恐怖を感じると、交感神経が活性化し、立毛筋が収縮して体毛が逆立つ。
これは哺乳類が外敵に対して体を大きく見せるための防衛本能の名残だ。
日本には平安時代から鎌倉時代にかけて漢籍とともに伝来し、江戸時代には怪談文学の隆盛とともに広く使われるようになった。
鶴屋南北の歌舞伎や、上田秋成の『雨月物語』など、恐怖を描写する文学作品において頻繁に登場する表現となった。
興味深いのは、この言葉が示す恐怖が「実際の危険」ではなく「想像上の脅威」に対しても同じように使われてきたことだ。
人間の脳は、現実の危険と想像上の危険を区別するのが苦手だ。
そして現代社会において、この区別の曖昧さが巨大な産業を生み出している。
それが保険だ。
データが明かす「恐怖」という幻想の正体
このブログでは、人間が抱く恐怖や不安の大半が統計的に極めて低い確率の事象に対するものであることを、複数の研究データと実際の統計を用いて検証する。
ミシガン大学の心理学研究チームが2019年に発表した論文によれば、人々が日常的に抱く心配事のうち85%は実際には起こらない。
さらに驚くべきことに、残り15%の「実際に起こった心配事」のうち、79%は当事者が想像していたよりもはるかに軽微な結果に終わっている。
つまり、私たちが抱く心配の約97%は、杞憂に終わるということだ。
それにもかかわらず、保険市場は世界的に拡大を続けている。
スイス再保険会社の2023年レポートによれば、世界の保険市場規模は約7.1兆ドル(約1,065兆円)に達し、過去10年間で年平均3.2%の成長を続けている。
この巨大産業は、人間の「起こりにくい事象への過剰な恐怖」を基盤に成立している。
本稿では、恐怖心理のメカニズム、統計的現実と心理的認識のギャップ、そして保険というシステムがいかにしてこの乖離を利用してきたかを、歴史的文脈とデータの両面から徹底的に解剖する。
人間が抱く恐怖の9割は統計的に起こらないという事実
ペンシルベニア州立大学の認知心理学者ロバート・リーヒ教授の15年にわたる追跡調査は、恐怖と現実の間に存在する巨大な乖離を数値化している。
調査対象となった3,200人の被験者に、日常生活で感じる不安や心配事を毎日記録してもらい、それらが実際に起こったかどうかを6ヶ月後に検証した。
結果は以下の通りだ。
心配事が実際に起こった割合は15%。
85%は起こらなかった。
起こった15%のうち、79%は被験者が想定していたよりも軽微な結果だった。
つまり、深刻な結果を招いた心配事は全体の約3%に過ぎない。
この現象を説明するのが「確率無視」と「利用可能性ヒューリスティック」という2つの認知バイアスだ。
確率無視とは、カーネマンとトヴェルスキーが提唱した概念で、人間は低確率の事象に対して確率を正確に評価できず、ゼロでない限り過大評価する傾向がある。
例えば、飛行機事故で死亡する確率は約1,100万分の1だが、多くの人が飛行機に恐怖を感じる一方で、自動車事故(死亡確率は約8,000分の1)に対しては比較的平静だ。
利用可能性ヒューリスティックは、記憶に残りやすい出来事ほど頻繁に起こると錯覚する傾向を指す。
メディアで大きく報道された航空機事故は記憶に残りやすく、そのため実際の確率よりもはるかに高い頻度で起こると感じてしまう。
チャップマン大学が2018年に実施した「アメリカ人の恐怖調査」では、1,190人の成人を対象に88項目の恐怖について質問した。
上位10項目は以下の通りだ。
政府の腐敗(74%)、環境汚染(68%)、医療費の高騰(67%)、テロ攻撃(41%)、愛する人の死(39%)、経済崩壊(37%)、身元情報の盗難(37%)、他人が自分について何を考えているか(33%)、核兵器(30%)、生物兵器(29%)。
興味深いのは、統計的に個人に降りかかる可能性が極めて低い「テロ攻撃」や「核兵器」が上位にランクインしている一方で、遥かに高い確率で起こる「交通事故」(年間死亡確率0.01%)や「心疾患」(年間死亡確率0.2%)は上位10位に入っていないことだ。
起こらない恐怖を商品化する3,000年の知恵
保険の歴史は、人間の恐怖心理を経済システムに組み込んだ壮大な実験だ。
最古の保険とされるのは、紀元前3000年頃のバビロニアで行われていた「冒険貸借」だ。
商人が船で貿易を行う際、貸主は航海が無事に終われば高い利子を受け取れるが、船が沈没した場合は元本を放棄する契約を結んだ。
これは現代の海上保険の原型だ。
近代的な保険システムの始まりは1666年のロンドン大火災だ。
この火災で13,200棟の建物が焼失し、7万人が家を失った。
翌年の1667年、ニコラス・バーボンという医師が世界初の火災保険会社「The Fire Office」を設立した。
バーボンのビジネスモデルは極めて合理的だった。
ロンドン全域で同時に火災が起こる確率は低い。
個々の建物が火災に遭う確率も低い。
しかし、人々は自分の家が燃える恐怖を抱いている。
ならば、その恐怖を少額の定期支払いに変換し、実際に火災が起きた少数の人に大きな補償を支払えば、数学的に利益が出る。
この「大数の法則」を活用したモデルは大成功を収めた。
1680年までにロンドンには複数の火災保険会社が設立され、競争が始まった。
生命保険の発展も同様の論理に基づいている。
1762年、イギリスで「Equitable Life Assurance Society」が設立され、死亡率表を用いた科学的な保険料計算を始めた。
数学者ジェームズ・ドドソンが開発したこの方式は、年齢別の死亡確率を統計的に算出し、それに基づいて保険料を設定するものだった。
ここで重要なのは、保険会社が賭けているのは「確率」であり、顧客が賭けているのは「恐怖」だという点だ。
保険会社は統計とデータに基づいて冷静に計算する。
一方、顧客は感情と不安に基づいて判断する。
この非対称性こそが、保険ビジネスの収益源だ。
現代日本の保険市場を見ると、この構造はより鮮明になる。
生命保険文化センターの2021年調査によれば、日本人の生命保険加入率は82.7%で、世帯年間払込保険料の平均は37.1万円だ。
しかし、実際にがん保険の給付を受ける確率はどうだろうか。
国立がん研究センターのデータによれば、30歳の人が10年以内にがんと診断される確率は男性0.5%、女性0.6%だ。
40歳でも男性2.0%、女性2.4%に過ぎない。
つまり、多くの人が年間数万円から数十万円の保険料を支払っているが、実際に給付を受ける確率は統計的に極めて低い。
この乖離が保険会社の利益を生み出している。
日本の生命保険会社の総資産は約400兆円で、これは日本のGDPの約75%に相当する。
金融庁の統計によれば、2022年度の生命保険会社全体の基礎利益は約3.5兆円だ。
この巨額の利益は、私たちの「起こらない恐怖」への支払いから生まれている。
恐怖を煽る産業構造
恐怖が商品化される過程で、メディアは重要な役割を果たしてきた。
ジョージ・ガーブナーの「培養理論」は、テレビ視聴時間が長い人ほど現実世界を危険だと認識する傾向があることを実証した。
彼の研究によれば、1日4時間以上テレビを見る人は、1時間未満の人に比べて、自分が犯罪被害に遭う確率を2.5倍高く見積もる。
実際の犯罪率との乖離はさらに大きい。
日本の刑法犯認知件数は2002年の約285万件をピークに減少を続け、2022年には約60万件まで減少している。
人口10万人あたりの犯罪発生率は約480件で、これは過去最低水準だ。
しかし、内閣府の「治安に関する世論調査」では、約60%の国民が「治安が悪化している」と回答している。
メディアが報道する凶悪事件の印象が、統計的現実を覆い隠している。
この認識の歪みは保険販売にとって好都合だ。
損害保険会社の犯罪被害保険や、傷害保険の販売は、実際の犯罪率の低下とは逆に増加傾向にある。
もう一つの典型例は地震保険だ。
地震調査研究推進本部の長期評価によれば、今後30年以内に南海トラフ地震が発生する確率は70~80%とされている。
この数字は確かに高い。
しかし、地震保険の加入率は2023年時点で35.4%だ。
つまり、実際に高い確率で起こりうる災害に対しては、人々は意外なほど備えていない。
一方で、はるかに低い確率の個別リスク(がん、死亡、火災など)に対しては高い加入率を示す。
この矛盾を説明するのが「心理的距離」の概念だ。
地震のような大規模災害は「いつか起こる」という漠然とした恐怖であり、具体的な日時が想像できない。
一方、がんや事故は「明日自分に起こるかもしれない」という具体的な恐怖として認識されやすい。
保険会社のマーケティングは、この心理を巧みに利用する。
「もし明日、あなたが事故に遭ったら」「もし突然、がんと診断されたら」といった広告は、抽象的な確率を具体的な恐怖に変換する。
アメリカの保険広告を分析した2017年の研究によれば、保険CMの67%が「損失の恐怖」を訴求ポイントにしており、「安心の獲得」を訴求するCMは33%に過ぎなかった。
人間は利益よりも損失に敏感に反応するという「損失回避性」を、広告戦略に組み込んでいる。
合理的なリスク判断とは何か?
ここまで見てきたように、人間の恐怖認識と統計的現実の間には大きな乖離がある。
では、私たちはどうすれば合理的にリスクを判断できるのか。
まず必要なのは「ベースレート」の理解だ。
ベースレートとは、ある事象が母集団全体で起こる確率のことだ。
例えば、「がん検診で陽性と判定された」という状況を考えてみよう。
多くの人は「がんである確率が高い」と感じる。
しかし、検査の感度(がんがある人を正しく陽性と判定する確率)が90%、特異度(がんがない人を正しく陰性と判定する確率)が95%、そして実際のがん有病率(ベースレート)が1%だとすると、計算は以下のようになる。
1万人を検査すると仮定する。
実際にがんを持っている人は100人(1%)。そのうち90人が正しく陽性と判定される(感度90%)。がんを持っていない9,900人のうち、495人が誤って陽性と判定される(特異度95%なので、5%の偽陽性)。
つまり、陽性と判定された585人(90人+495人)のうち、実際にがんを持っている人は90人だけだ。確率は約15.4%に過ぎない。
この計算ができる人は驚くほど少ない。
ハーバード大学の研究によれば、医師でさえ60%以上がこの種の確率計算を誤る。
一般人ではさらに正答率が低い。
次に重要なのは「比較可能なリスク」の把握だ。
単独の確率は判断材料にならない。
他のリスクと比較して初めて、その大きさが理解できる。
以下は、アメリカ国家安全評議会が発表した「生涯で死亡する確率」の比較データだ。
心疾患による死亡は6分の1。
がんによる死亡は7分の1。
交通事故による死亡は107分の1。
転倒事故による死亡は106分の1。
銃による死亡は289分の1。
オートバイ事故による死亡は890分の1。
火災による死亡は1,547分の1。
溺死は1,121分の1。
航空機事故による死亡は9,821分の1。
落雷による死亡は15,300分の1。
このデータを見れば、何を恐れるべきかの優先順位が明確になる。
しかし、多くの人は航空機事故を恐れる一方で、日常的な転倒や心疾患のリスクを軽視する。
三つ目のポイントは「期待値」の計算だ。
期待値とは、確率と結果を掛け合わせた数学的な期待リターンのことだ。
例えば、月額3,000円のがん保険に30年間加入すると、総支払額は108万円になる。
一方、がんと診断されて給付金300万円を受け取る確率が10%だとすると、期待値は30万円だ。
つまり、統計的には78万円の損失が期待される。
もちろん、保険は期待値だけで判断すべきものではない。
「万が一の時の経済的破綻を避ける」という価値もある。
しかし、その価値が78万円に見合うかどうかは、個々人が冷静に判断すべきだ。
まとめ
毛骨悚然という言葉が示すのは、人間の恐怖が理性を超えて身体反応にまで及ぶということだ。
しかし、その恐怖のほとんどは統計的に起こらない。
ではなぜ私たちは恐怖を感じ続けるのか。
それは進化の過程で獲得した生存戦略だからだ。
原始時代、目の前の危険を過小評価すれば即座に死に繋がった。
一方、危険を過大評価しても失うものは少なかった。
だから私たちの脳は、リスクを過大評価するようにプログラムされている。
この傾向は、現代社会では必ずしも有利に働かない。
統計的に極めて低い確率の事象に過剰な資源を投入すれば、本当に重要なリスクへの備えが疎かになる。
保険は、この心理的傾向を利用した精巧なシステムだ。
私たちの恐怖を集約し、数学的に再分配することで、社会全体のリスクを管理する。
その意味で、保険は価値あるシステムだ。
しかし同時に、保険業界は私たちの認知バイアスを増幅させることで利益を得ている。
恐怖を煽るマーケティング、複雑な契約条件、統計的現実とかけ離れた保険料設定。
これらは、情報の非対称性を利用した搾取の側面も持つ。
私たちに必要なのは、恐怖を否定することではなく、それを認識した上でデータと確率に基づいて判断することだ。
毛骨悚然とする感覚を持ちながらも、その感覚に支配されない知性を持つこと。
ミシガン大学の研究が示したように、私たちの心配の97%は杞憂に終わる。
残りの3%に備えることは重要だが、97%のために人生の資源を浪費すべきではない。
保険に年間37万円を支払う日本人の平均像を思い返してみよう。
その金額を30年間投資すれば、複利効果により1,500万円以上の資産になる可能性がある。
もちろん、必要な保険まで削るべきではない。
しかし、恐怖に駆られた過剰な保険加入は、長期的には大きな機会損失を生む。
恐怖は、古代中国の時代から人間を支配してきた。
しかし同時に、人間は数学と統計という武器を手に入れた。
毛骨悚然の先にあるのは、データに基づいた冷静な判断と、本当に重要なことへの資源配分だ。
保険という巨大産業は今後も存在し続けるだろう。
それは人間が恐怖を感じ続ける限り、需要があるからだ。
しかし、その構造を理解し、自分自身の判断基準を持つことで、私たちは恐怖に支配されない選択ができる。
毛骨悚然とする瞬間はこれからも訪れる。
しかしその時、統計的事実を思い出し、深呼吸をして、データを見る。
それが現代を生きる私たちに求められる知恵だ。
【X(旧Twitter)のフォローをお願いします】