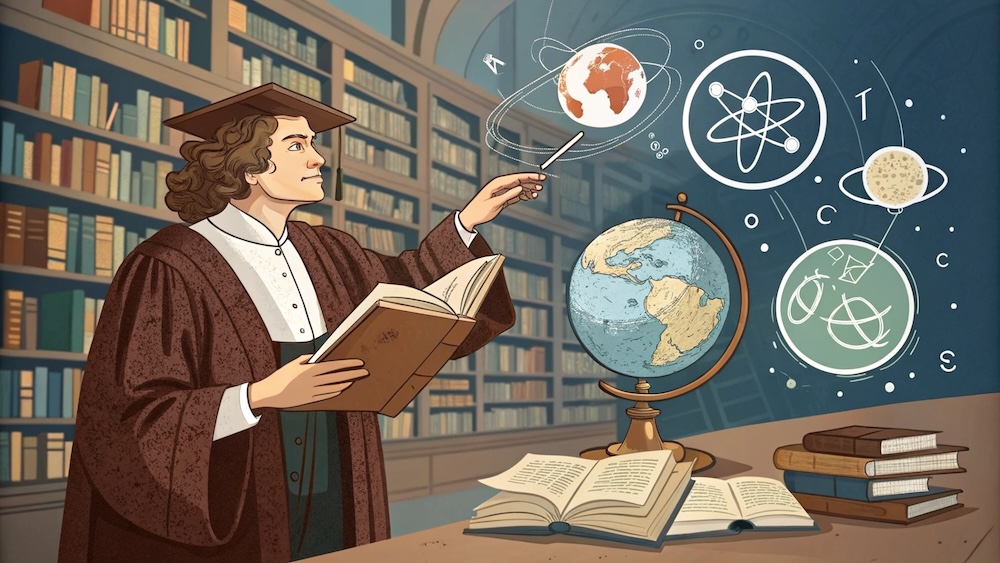百家争鳴(ひゃっかそうめい)
→ 学術界におけるさまざまな立場の学者、論客が論争しあうこと。
世の中には無数の問題や疑問が渦巻いている。
そこに「学者」と呼ばれる人々が多種多様な観点から切り込み、研究し、新たな知見を提示してきた歴史がある。
一方、「学者」とは厳密にはどう定義されるのかを深く考えたことがある人は多くないかもしれない。
私と同様に斬新な発想や数値データに基づく意思決定を重視しているが、学者という肩書きの持つ奥深さには常々興味を抱いている人も少なからずいるだろう。
そこで、今回は「百家争鳴」という概念の背景をひも解きながら、学者の定義と現状に関する世界と日本の比較データを提示し、学問領域がどう広がってきたのか、そしてそこにどんな問題が横たわっているのかを明らかにしていく。
そもそも、百家争鳴の始まりは中国の戦国時代や春秋時代に端を発するとされる。
孔子や老子、墨子、荀子など、数多くの思想家がそれぞれの哲学や政治論を展開し、多くの学派が乱立した状況を示す言葉だと思われがちだが、実際には毛沢東時代のスローガン「百花斉放、百家争鳴」から来ているという説も存在する。
いずれにせよ、「無数の思考が同時多発的に争い、議論を巻き起こす」という点にこの言葉の核心があることは間違いない。
ここから読み取れるのは、多様な思想や理論が同時に存在する状況は決して現代特有ではなく、古来から繰り返し起こってきたという事実だ。
情報伝達手段こそ違えど、あるテーマに対してそれぞれの専門家や賢者が自らの知見を競い合う構図は、歴史を通して変わらず存在した。
一方、この概念が現代社会においても通用するのは、あらゆる領域で専門家が増え続けていることに起因している。
学術界の裾野が拡大し、多種多様な専門領域が確立されていくほどに、それぞれの研究分野をめぐる議論は増幅していく。
これは人類の知的資産が拡充されることを意味すると同時に、知識が細分化されすぎることで全体像が見えにくくなるという新たな問題も抱えている。
とううことで、学者という存在の定義を掘り下げ、「なぜ百家争鳴の様相が強まっているのか」を考察したい。
学者とは何者か:多彩な定義と学術界のリアル
「学者」という言葉を辞書的に見ると、「学問を専門に研究する人」といったシンプルな説明が多い。
大学教授や研究機関に所属する研究者、あるいは独立したシンクタンクで活動する専門家など、広範な領域を含む概念だ。
だが、実際に学術界を見回すと、理系・文系、あるいは人文科学・社会科学・自然科学、さらには工学系・医療系など、きわめて多岐にわたるジャンルが存在する。
私がCEOとして事業を運営する中でも、IoTやAIなどのテクノロジーに特化した研究者と、社会学や心理学の視点から事業戦略に切り込む研究者では、全く異なるアプローチがあると日々感じている。
学者をもっと正確に捉える上で考慮すべき要素を挙げると、以下のようになる。
- 研究分野(自然科学、社会科学、人文科学など)
- 所属(大学、研究機関、企業の研究部門、独立系など)
- 研究の目的(純粋探求、応用研究、コンサルティング、公共政策立案など)
- 活動領域の広さ(単一の分野に特化、あるいは学際的・横断的)
たとえば企業の研究所で働く専門家は「研究員」と呼ばれることが多いが、大学や研究機関のポストを持たない非常勤の研究者やポスドクも存在する。
さらには研究活動を続けつつ起業する人も増えており、個々のキャリアパスは多彩な選択肢であふれている。
こうした多様性が学術界の厚みを生み出している一方、「学者」と一口にまとめるには無理が生じやすい。
では、実際に世界にはどれほどの数の学者が存在し、どの領域に偏在しているのかを具体的なデータで見ていく。
世界と日本の学者数を示す視覚データ
まずは問題提起として、世界と日本の学者の数を比較するデータをいくつか紹介する。
ここでは、国際連合教育科学文化機関(UNESCO)が公表している研究者数や、日本国内では文部科学省や日本学術振興会(JSPS)のデータ、あるいは総務省が出している統計資料などをもとにした推計値を参照している。
数字は最新とは限らないが、全体像を把握する上での目安として紹介する。
世界全体の研究者数(研究開発職を含む)に関するおおまかな推計
- 世界全体:およそ800万人~900万人
- 主要国別割合(目安)
- アメリカ:約25%
- 中国:約20%
- ヨーロッパ(EU全体):約25%
- その他地域:残り30%
日本の研究者数(研究開発職を含む)
- 日本全体:およそ85万人~90万人(企業研究者を含む)
- 大学教員(専任ベース):約18万人
- 独立行政法人や国公立研究機関など:数万人規模
これらは「研究者」という枠組みなので、いわゆる「学者」とほぼ同義とみなすには少々議論がある。
とはいえ、学術活動に携わる層の大部分はこの中に含まれるため、学者人口の大きな指標になる。
特に日本では企業の研究部門に所属する技術者・研究者の数が多い点が特徴で、大学を出て民間企業に入った後も研究活動に近いことを行うケースが少なくない。
ここで示したデータの通り、世界各国が知的競争を繰り広げる中で、学者や研究者と呼ばれる人々が年々増加している。
一方で、純粋な学問を極める立場というよりも、社会実装やビジネスへの応用を重視する動きも顕著になっており、「学者」の概念はますます複雑化している。
これがまず最初の問題提起と言えるだろう。
学術領域の偏在と拡散がもたらす問題
なぜこのように学者や研究者が増え続けるのか。
大きな要因として、国家や企業が研究開発投資を拡大している事実が挙げられる。
特にITやバイオテクノロジー、ナノテクノロジーなどの先端分野では、グローバル企業が巨額のR&D費用を投下しており、それによって新しい専門領域が次々に生まれている。
そこに新たな研究者ポストが生まれ、結果として学者人口が膨張していく構図だ。
しかし、問題はそれだけではない。
研究テーマが細分化されればされるほど、他分野との対話が難しくなる。
たとえばAIの研究者が自然言語処理や画像認識の分野に特化するあまり、哲学や倫理学の研究者と議論する機会が減れば、社会課題の総合的な解決が遅れる恐れがある。
また、予算獲得や成果主義のプレッシャーにさらされ、学者自身も専門領域に閉じこもりがちになる傾向が強まるという声も聞こえてくる。
このように、学者数が増えること自体は知的資産の拡充という意味で大いに歓迎すべき側面を持つ。
一方、分野の分断と専門家同士のコミュニケーション不足が「百家争鳴」の良さを無にしてしまう可能性がある。
多様な知見が出そろうだけでは不十分で、それを統合し、新たな価値を生むための仕組みが必要というわけだ。
さらに、下記のようなデータも問題を浮き彫りにする。
ジャンル別の研究者割合(あくまで世界的な推計)
- 自然科学・工学系:全体の約60%
- 医療・生命科学系:約20%
- 社会科学系:10%弱
- 人文科学系:5%以下
- その他学際領域:数%
この数字は国や地域によりばらつきがあるが、工学や生命科学といった経済発展や医療に直結しやすい分野に研究者が偏り、社会科学や人文系が後回しにされる傾向が見え隠れする。
学者が増えているとはいえ、その分布は均一ではなく、これが「社会全体の物事を学術的に俯瞰する視点の不足」につながりやすい。
問題は学者が多いか少ないかだけではなく、その分野間のアンバランスが生む影響にこそある。
別のデータから読む知の衝突と統合のジレンマ
分野のアンバランスだけでなく、学者同士の対立や議論がどう生まれるのかを読み解く上で、論文引用データや学会の発表件数などを追うと面白い事実がわかる。
たとえば世界的に権威ある学術ジャーナルに掲載される論文数を見ると、自然科学や工学系が圧倒的に多いのは明らかだが、そこに属する個別テーマは極端に細分化されている。
細分化された領域内では熾烈な競争があるものの、隣接する分野との交流は少ないという分析結果もある(学術ネットワーク解析を手がける研究機関の報告より)。
この状況はある意味、「百家争鳴」の形骸化を示しているかもしれない。
数だけ見ると学者は増加しており、対立や議論も増えているように見える。
だが実際には、同じ専門領域内での狭い議論に終始してしまい、異なる学派や多様な意見が交わる「知の総合」が実現しにくくなっている。
研究費や学会の評価基準、出版物の評価など、学術システムそのものに構造的な問題があると言えるだろう。
しかし、そうした制約の中でも、学際研究を推進しようとする動きも高まっている。
データサイエンスが多様な学問領域を横断するツールとなり、社会科学や人文科学の分野でもビッグデータを活用し始めている事例が増えている。
IoTやAIの開発においても、センサー技術やネットワーク工学だけでなく、人間心理やデザイン思考など、異なる領域との連携が鍵を握っているのは確かだ。
実際、私がstak, Inc.のCEOとして携わる事業においても、純粋なハードウェアやソフトウェアの研究だけではなく、マーケティングや社会学的アプローチが必要不可欠だと痛感している。
まとめ
ここまで世界と日本の学者数の推計データや、ジャンル別の分布、さらに学術界の構造的な問題を見てきた。
その結論として、百家争鳴は単に「学者が増えて議論が活発になる」ことを意味するだけではないと考えている。
むしろ、学問の細分化や専門領域の偏在によって本来の多様な知見の統合が妨げられ、形だけの争鳴に陥るリスクがあることが重要な示唆だ。
一方で、データを見る限り、工学や医療分野を中心に学者数が着実に増えている事実は、人類が新技術や新知見を獲得する推進力になっているとも言える。
このエネルギーをいかに社会全体で活かしていくかが、今後の焦点となる。
特にAIなどの先端テクノロジーによって分野横断的なコラボレーションが容易になる可能性は高く、ここを活用できるかどうかが大きな分かれ目になる。
stak, Inc.としては、自社製品を通じて誰もが気軽にIoTの恩恵を受けられる世界を目指しているが、それを実現するには工学的知識とビジネス的視点だけでは足りない。
心理学やデザイン学、さらには社会科学の知見を取り込み、人間とテクノロジーのあり方を再定義していくことが不可欠だ。
こうした学際的な取り組みが増えれば増えるほど、専門外の学問領域を持つ学者との協働も進むはずであり、そこに本来の「百家争鳴」の意義が生まれてくる。
「百家争鳴」とは決して、各々が好き勝手に意見をぶつけ合う混乱状態を表すだけの言葉ではない。
むしろ、多様な知を結集し、深い洞察やイノベーションを生み出すための基盤だと捉えられる。
データが示す通り、学者の数は増え続け、世界規模で知識の専門化が進行している。一方で、その多様性を真に活かすためには分野横断的な対話と協働を促進する仕組みが必要だ。
最後に、「学者」と呼ばれる存在は想像以上に幅広く、研究機関や大学だけでなく企業や独立系のシンクタンクなど多彩な場で活躍している。
そして、ジャンルの偏在や細分化の進行は、学術界における真の意味での百家争鳴を難しくしている。
しかし、データサイエンスなど新しいツールの普及や学際研究への関心の高まりにより、今後はより多様で柔軟な「知の共創」が求められる。そこにこそ、社会を変革する大きな原動力があると確信している。
学問が人類の未来を左右する要因のひとつである以上、学者の存在がいま以上にクローズアップされる時代はさらに続くはずだ。
だからこそ、一見派手にぶつかり合うように見える「百家争鳴」の背景には、深くつながり合う知のネットワークこそが必要になる。
自分たちの事業も、そのネットワークの一端を担う存在として成長していくことを強く意識しながら、新しい時代のイノベーションを生み出していきたいと考えている。
【X(旧Twitter)のフォローをお願いします】