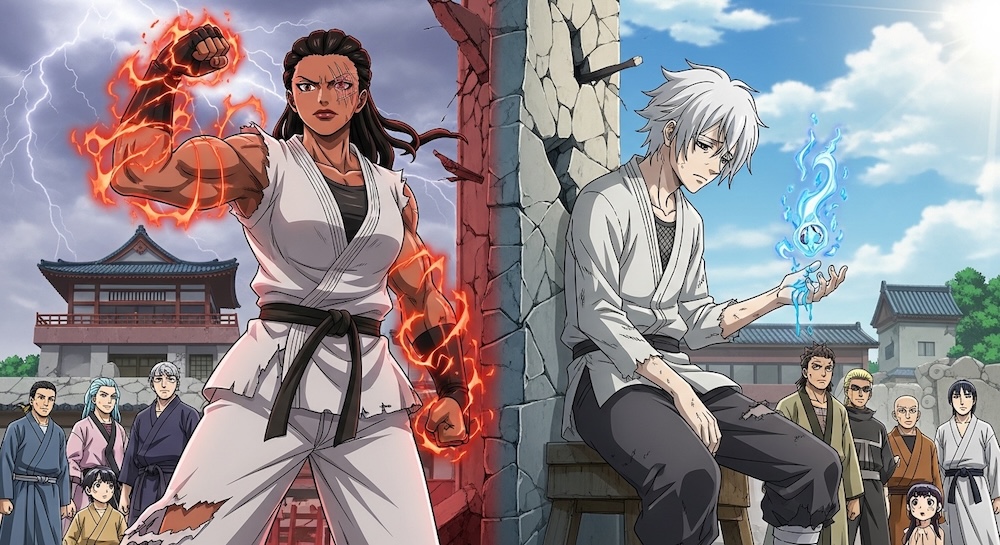氾愛兼利(はんあいけんり)
→ すべての人をあまねく愛し、利益をともに分けあうこと。
氾愛兼利とは、すべての人をあまねく愛し、利益をともに分け合うという理想を掲げた言葉とされる。
日本語圏で見かける例としては中国の古典に見られる「兼愛交利」や、孔子・孟子などの思想に通じる内容がある。
ただしこの言葉は日本の文献や辞典などでは見つかりにくい場合もあるため、その起源を追うにはやや工夫が必要になる。
ここでは氾愛兼利という概念がどう生まれ、どのように伝播してきたかを探る。
まず、東洋思想では「博愛」「仁愛」「慈悲」など、人を広く愛する概念が古くから存在した。
代表例としては、古代中国の思想家・墨子の「兼愛説」がある。墨子はすべての人を平等に愛することを説き、戦争や差別を強く批判した。
兼愛説の一部には「利を分かち合う」要素も含まれており、個人の利益だけでなく社会全体が利益を共有する姿を理想とした。
これが「氾愛兼利」と呼ばれる考えと通じる面があるとされる。
さらに西洋圏でも、キリスト教の「博愛」(Agape) や、フランス革命時に掲げられた「自由・平等・友愛」(Liberté, Égalité, Fraternité) が近しい考え方だと言える。
愛を広く分かち合い、利益を皆で得るべきだという理想は、宗教・政治・哲学を問わず世界各地で唱えられてきた。
こうした博愛や共有の概念は多くの国や社会運動で掲げられ、人類史を通して思想や社会の大きな原動力にもなっている。
しかし、どんなに「博愛」や「兼愛」が唱えられてきたとしても、歴史を振り返ると差別や搾取、戦争が繰り返されてきたのも事実だ。
国内外の文献や史実を見渡すと、あまねく愛し合う社会を作ることがいかに困難であるかが浮き彫りになる。
古代や中世には、王侯貴族や特権階級が富を独占し、庶民には利益を与えない制度が長く続いた。
近代以降になっても、帝国主義や植民地支配のもとで他者から資源を奪い、富を独占する国が多数あった。
実際に、第一次世界大戦や第二次世界大戦の時代を経ても、人間は争いを絶やすことができなかった。
国連やさまざまな国際機関が平和や人権を訴えても、利害調整が難航し、現在でも国際紛争は起きている。
これこそが、「氾愛兼利」の理想と人類の現実のギャップを示すエビデンスだと言っていい。
一方で、経営やIT、AI、IoTなどの領域を見渡すと、人類の知恵やテクノロジーが進歩したにもかかわらず、完全なる「博愛社会」には程遠い。
この大きな原因としては、国家や企業、個人が自らの利益を優先したい本能が常に働くという点がある。
こうした事情を踏まえれば、「氾愛兼利」が目指すところは明確だが、決して容易に実現できるものではないとわかる。
あまねく愛する・利益をともに分け合う理想
「あまねく愛する」「利益をともに分け合う」には多くの四字熟語やことわざが存在し、世界中で同様の理想が掲げられてきた。
日本なら「和衷協同」「相互扶助」、英語なら「Sharing is caring」、さらにドイツ語圏では「Mitmenschlichkeit」(人間性を大切にする) など枚挙にいとまがない。
こうした言葉やフレーズは、それぞれの文化で人間同士が助け合うことの大切さを説いている。
現代においてはSDGs (持続可能な開発目標) やESG投資の広がり、ソーシャルビジネスの浸透など、「みんなで利益を分かち合おう」という価値観はさらに強まっている。
特にITやAI、IoTなどの技術が社会インフラとなった今、オープンソースのソフトウェアやクラウドサービスのように、情報資産を共有しながら社会を発展させようという動きも見られる。
実例として、Linuxカーネルなどのオープンソースソフトウェアは、世界中のエンジニアが協力して開発と改良を続け、巨大なエコシステムを築いた。
利益をともに分け合うという点で、このようなオープンソース・コミュニティは「氾愛兼利」の概念に近い部分がある。
誰でも利用できる基盤を共有し、そこから生まれる成果は開発者全員に還元される仕組みは、多くの企業が恩恵を受けてきたと言える。
ただし理想が理想として語られるほど、それがどれほど実現困難かも強調されてしまう面がある。
技術コミュニティが成長すればするほど、利害調整が難しくなることは歴史が示している。
プロジェクトの中心メンバーが利権を握り、新参者が参入しづらくなったり、思想の違いから大きな対立が生まれたりするケースも枚挙にいとまがない。
オープンソースの世界ですら、「コミュニティの中心人物」が絶大な力を持ちすぎて問題になることは実際に起きている。
理想を描けば描くほど、それを実現するための壁も厚く高くなる。
だからこそ、そんな完璧な「聖人君子ばかりが集う世界」というのはそもそも空想上のものではないか、と疑念を抱くのも自然なことだろう。
極端な例として、かつての社会主義国家や共産主義体制の失敗がある。
建前としては「みんなで平等に利益を分かち合う」ことを標榜しながら、実際には特権階級が存在して格差が拡大したケースは歴史上多数ある。
世の中にそんな聖人君子はいないのではないかという疑義
氾愛兼利が理想であることは間違いないが、実際にそれを体現できる「聖人君子」は本当にいるのだろうか。
歴史上において、聖人君子とされる人物は多数存在する。
例えば、インド独立の父とされるマハトマ・ガンディーは「非暴力・不服従」を徹底し、人々から崇拝された。
しかし、ガンディーもすべての人間関係を完全に愛で満たしていたわけではなく、同時代の政治的対立や個人の意思の衝突が絶えなかったという事実もある。
日本史でいえば、聖徳太子が掲げたとされる「和を以て貴しと為す」という十七条憲法の理念は博愛に近いが、実際の政治や権力闘争の中でどこまで厳守されたのかは疑問視される。
さらに、聖徳太子が本当に存在したのか、複数の人物のモデルを合成した可能性があるという学説もあるほどで、歴史の闇は深い。
こうした事例を紐解くと、道徳的に高い理想を説く人物ですら、多くの制約や時代背景、個人的事情に左右される。
まったく私利私欲を持たない人間がいると考えるのは、現実としてはかなり難しいだろう。
むしろ、人間は欲望を持ってこそ行動のエネルギーを得る部分もあるため、完全に欲を排した存在などほとんどいないのではないか。
これが「そんな聖人君子などいない」という疑義を多くの人が感じる理由である。
経営やビジネスの観点から考えても、利益を求める姿勢は企業活動の根幹にあるため、「すべてを分かち合う」ことは難しいのが現実だと言える。
特にスタートアップやベンチャー企業は投資家からの出資を受けている場合が多く、株主の利益を無視して理想だけを追求するわけにはいかない。
ITやAI、IoTなどの技術開発においても、開発コストや知的財産の問題が絡んでおり、利益配分は非常にシビアなバランス調整が必要になる。
このあたりの現実的な問題を無視して「すべてを愛し、すべてを分かち合う」と言われても、それは綺麗事と捉えられても仕方がないだろう。
実際、日本国内で2019年に一般社団法人日本経済研究センターが行った調査によれば、「自社の利益と社会の利益のどちらを優先させるか」という問いに対し、回答企業の約73パーセントが「自社の利益を優先せざるを得ない」と答えている(日本経済研究センター「企業意識と社会貢献に関する調査」2019)。
これはまさにビジネスの論理が理想や博愛と衝突する実例といえる。
性善説・性悪説が示す人間観の議論
氾愛兼利を否定的に見る側の根拠としてしばしば持ち出されるのが、性善説と性悪説の議論である。
この議論は古代中国において孟子と荀子が大きく対立したことで有名だが、それ以前からも人間の本性についての議論はあった。
性善説とは「人は生まれながらにして善なる本性を持つ」という考え方であり、孟子やルソーなどが支持した。
一方、性悪説は「人は生まれながらにして悪の性質を持っている」という考え方で、荀子やホッブズなどが傾倒してきた。
さらに日本では江戸時代の儒学者・荻生徂徠が性悪説寄りの立場をとったこともあり、江戸期の政治や道徳観念に大きな影響を与えた。
実際に、この性善説か性悪説かという論争は一筋縄ではいかない。
近年の神経科学や心理学の研究では、人間には利他的行動を取る傾向が先天的に備わっている一方で、集団で排他主義的行動をとる傾向もあると指摘されている。
アメリカの心理学者マイケル・トマセロの研究によると、幼児はとても早い段階から他者を助けようとする行動を見せるが、同時に自分と利害が衝突するときには攻撃性を示すこともあるという。
これらは性善説と性悪説の両方の側面を内包しているとも解釈できる。
一方で、それらの議論がいつから本格化したのかを歴史的に紐解くと、少なくとも紀元前4世紀ごろの中国で既に芽生えていた。
孔子や孟子、荀子といった諸子百家が活躍した戦国時代には「人間の善と悪」が社会秩序を左右する重要なテーマだったとされる。
その後、儒教が中国や東アジアの中心思想として確立される過程で、性善説・性悪説の対立は「人間はどうあるべきか」という道徳論の骨格にもなっていった。
ヨーロッパでも、キリスト教神学において「原罪」や「慈悲」など、人間の本性をどう捉えるかは大きなテーマだった。
ホッブズの「リヴァイアサン」(1651年) での「人間は自己保存の欲求をもち、自然状態では万人の万人に対する闘争になる」という理論は、事実上の性悪説と捉えられる。
一方でルソーは18世紀に著書「エミール」(1762年) などで「人間は本来善であるが、社会によって堕落する」という考えを示した。
これらの思想はその後の啓蒙主義にも影響を与え、人間観の議論として長く続いている。
こうして考えると、性善説か性悪説かという議論は、古今東西を問わず人間社会に根付いているテーマだとわかる。
何世紀もの間、人々は人間の本性が善か悪かをめぐって議論を重ね、そこに合わせて社会制度や道徳教育を設計してきた。
そのこと自体が、すべての人をあまねく愛し、利益をともに分かち合う社会を築くことの困難さを示すエビデンスでもある。
中庸思考とコミュニティ内性善説の提案
では「性善説と性悪説の中間に立つ考え方」こそがいいのではないか、という意見もある。
確かに、人間は善にも悪にもなりうる存在であり、状況や環境によって行動が変わるという見方は比較的しっくりくる。
いわゆる中庸思考は「両極端を避け、適切なバランスを取ることが大切」というアリストテレスの徳倫理学の考え方にも通じる。
しかし、この中庸思考も「どっちつかず」だと批判されることが多い。
性善説か性悪説かをはっきりさせないまま「まあ中間くらいだろう」と言うのは、一見柔軟に見えるが実行段階では曖昧さが残る。
要するに、議論を深めることを避けているだけではないかと言われても仕方がない。
そこで、私自身の持論として提案したいのが「コミュニティ内性善説」という考え方だ。
これは、自分が直接関わるコミュニティにおいては、相手を信頼して接することを基本とするという立場であり、無差別に誰彼構わずという博愛主義ではない。
しかし、身近な範囲では相手を尊重し、助け合い、利益を分かち合う関係性を目指す。
いきなり全人類を愛するという大きすぎるスケールを掲げるのではなく、自分が関わる領域の中で誠実に行動することを第一とするわけだ。
この考え方は、スタートアップや中小企業にも通じる部分がある。
大企業が巨大なリソースを抱え、大きな影響力を振るう中で、小さな企業が生き残るには「小さなコミュニティの中で互いを信頼し、相互扶助で成長する」しか道がないとも言える。
特にITやAI、IoTの世界では、クリエイティブな発想や連携プレイが勝利の鍵になる場合が多い。
そこで、身近な仲間やコミュニティメンバーを信頼し、お互いの利益をしっかり共有する取り組みを行うことで、結果的に大きな成功につなげることも期待できる。
実際に、成功したベンチャーの多くは、「創業メンバーの間に強い信頼関係がある」「初期ユーザーコミュニティを大切にしている」といった共通項がある。
たとえばアメリカのTwitter社が創業期に非常に小さなコミュニティから始まり、ユーザー同士が機能改善のアイデアやハッシュタグを生み出していった事例は有名だ。
ハッシュタグはユーザーのアイデアだったが、そこから「コミュニティによるサービス拡張」が起こり、Twitterは世界的なSNSになった。
小さなコミュニティでの性善説的な協力が、大きな成果を生む好例ともいえる。
こうした事例を見ると、人間が欲望を完全に無くして博愛主義になるのは難しいが、コミュニティレベルでの相互扶助や愛情深い行動は十分に現実的に可能だとわかる。
これが「コミュニティ内性善説」を推す理由だ。大規模に「氾愛兼利」を実現するのは難しくても、小規模な単位でなら似たような結果を生み出せる可能性が高いと考えている。
まとめ
ここまで、氾愛兼利という概念が生まれた歴史や背景、そして性善説・性悪説の議論を徹底的に振り返った。
あまねく人を愛し、利益をともに分け合うというのは確かに美しい理想だが、歴史や現実のデータを見れば、それがいかに困難かが浮き彫りになる。
長い人類史においても、全員が博愛主義者という時代が実現したことは一度もない。
性善説・性悪説の議論は紀元前からすでにあり、東洋でも西洋でも多くの思想家や哲学者が論じてきた。
この長い議論の歴史と、現代の心理学や脳科学が示す知見を合わせれば、「人間には善悪両面がある」という見方が妥当だろう。
ここから、中庸思考やコミュニティ内性善説といった「ある程度割り切った」スタンスが生まれるのは自然な帰結といえる。
私自身は、「まずは目の前のコミュニティから性善説で臨み、お互いの利益を共有していく」ことを提案する。
その先に、もう少し広い世界へと手を伸ばしていく過程で、相互の信頼関係が大きな利益を生み出す可能性もあるだろう。
IoTやAIなどのテクノロジーがさらに進化し、人と人とのつながりや情報共有が容易になる時代だからこそ、コミュニティ内の凝集力でイノベーションを起こせる環境が増えるはずだ。
そのうえで「氾愛兼利」を目指す大義名分を否定する必要はないが、あたかもそれが当たり前かのように強制するのは押しつけがましい。
むしろ「そんな完璧な聖人君子などそうはいない」という現実を見据えつつ、小さな単位で理想を実践してみる。
こうして一人ひとりが、自分の手が届く範囲でなら、お互いを尊重し合い、愛を持って接し合える関係性が築けると信じている。
これが、経営やIT、AI、IoT、そしてマーケティングなどの知識を踏まえたうえで私がたどり着いた結論だ。
小さく始めて大きく育てるというスタートアップの基本戦略とも共通する考え方であり、コミュニティの持つ力を信じるからこそできるアプローチだと思う。
ここに私の私見を重ねて締めくくりたい。氾愛兼利がただの理想で終わるのではなく、現実に即した形で少しずつ広がっていく可能性は十分にある。
ただし、その実現には「小さなコミュニティから始める」視点と、お互いを尊重し合う強い意志と行動が不可欠なのだ。
以上が、すべての人をあまねく愛するという美しい理想が歴史的にどう語られ、現実のデータや議論が何を示しているのかを踏まえたうえでの、私の持論である。
今後もこのテーマは議論の種であり続けるだろうが、自分が関わる小さなコミュニティの中で性善説を体現し、その価値を証明していくことが、遠回りのようで実は最も実効性のある道だと信じている。
こうした姿勢で取り組むときこそ、新たなビジネスチャンスやイノベーションに巡り合う可能性も増えていくはずだ。
【X(旧Twitter)のフォローをお願いします】